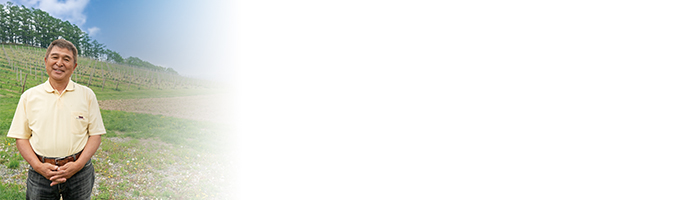経営に役立つコラム
経営に役立つコラム
【賢者の視座】株式会社OcciGabi Winery 落 希一郎
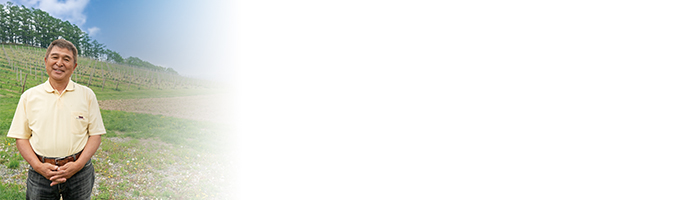
欧州のワイン作りに魅せられ50年。
日本に本場のワイナリーを実現させたい。
株式会社OcciGabi Winery
落 希一郎
日本人の食生活にワインが定着する以前から国内で独自にワイン作りを始めた落希一郎氏。
現在、株式会社OcciGabi Wineryの専務取締役として北海道・余市の地でワイン作りとワイナリー経営の手腕を発揮する。尚、社長は愛妻 落雅美氏。社名は彼女の名に由来する。
私にできるのはワイナリー作りだけ。いつか余市を日本のナパバレーにしたい。

北海道余市町と聞けば、ニッカウヰスキーの余市蒸留所を思い浮かべる人が多いのではないだろうか。近年、地球温暖化の影響を受けてワインに必要なブドウ栽培にも適した地となり、余市町では日本有数のワイン産地を目指して官民挙げての取り組みが進んでいる。2011年には国の構造改革特別区域法による「北のフルーツ王国よいちワイン特区」に認定され、ワイナリーの数も10軒あまりに増加。その中で「OcciGabi(オチガビ)ワイナリー」の落希一郎専務はワイナリー経営塾を運営し、同地のワイナリー作りに大きく貢献した人物だ。
落専務は現在70歳。64歳のとき、およそ6億円の借金をして、オチガビワイナリーを一から創り上げた。現在、ワイナリーには広大なブドウ畑と、その中心に地下醸造所を備えた瀟洒(しょうしゃ)なレストランがあり、ワインの製造・販売と飲食業を行っている。
ブドウ作りから醸造まで 当主が手がけるのがワイナリー
そもそも落専務とワインの出会いは偶然の巡りあわせだった。小樽で繊維問屋を営んでいた落専務の義理の叔父が山梨のブドウ農家の出身で、いずれ日本に本格的なワイナリーを作りたいという夢を持っていた。しかし、当時はワイン用のブドウ栽培もワインの醸造技術も日本で学べる場所がない時代。そこでその叔父が持ちかけてきた海外留学という言葉に惹かれて、落専務は叔父の会社に勤めはじめる。3年半後、念願の海外留学が決まり、向かった先はドイツ・シュツットガルトにある国立ワイン学校だった。
「当時欧州のブドウ栽培の北限がドイツで、北海道でのワイン作りに役立つと考えてのことでした。全寮制で2年間、みっちりワイン作りに関するすべてを学びました」
国立ワイン学校での2年間は、その後の落氏のワイン作りの礎となる。まず「ワイン作りは畑作りである」ということ。
「ワインの味の99%は、原料であるブドウで決まります。ワインの本場ではブドウを栽培している人がワインを作る。ここが日本酒造りとの大きな違いです。日本酒の原料は米ですが、酒造会社が米作りまですることはありませんし、当主が原料をいじることもないでしょう。一方、ワイナリーは全世界で6 0 万軒あるといわれていますが、どこも自分たちでブドウを栽培し、ワインの醸造から瓶詰めまで当主が担当します。当主が畑に出られなくなったら、交代するのが一般的なんです」
そして「ワインは少量生産・少量販売する商品である」という考え方だ。ドイツではシュツットガルトのような大都市でも、少し郊外へ行けばブドウ畑が広がり、ワイナリーが点在する。人々は好みのワインを求めてワイナリーを訪ねて回り、必ず試飲し、当主よりその年のワインについて説明を受けてから購入するという。
「ワインは毎年味が違う。ですから試飲のない販売はあり得ません。ワインは料理と同じなんですよ。同じレシピで同じ人がつくっても、料理は毎回微妙に味が違いますよね?それと同じで大量生産する商品ではなく、古代的な流通を通らざるを得ない産物なんです」
ワイナリーの好適地を求め、北海道から長野を経て新潟へ
ワイン学校で学ぶと同時に欧州や北米のワイナリーを訪ねて見識を広めた後、落専務が帰国したのは1977年。さっそく叔父の会社が所有する北海道・浦臼の土地でブドウ畑作りからスタートさせた。当初、「寒冷な北海道でワインなどできるわけがない」と業界から冷ややかな目で見られたチャレンジだったが、寒冷地に強いブドウの苗を使い、土壌改良や野生動物対策に苦労しながら、2年後には自家栽培・自家醸造のワイン生産に成功。落専務のワインは驚きの目を持って迎えられた。
その後も北海道でのワイン作りは10年続く。「作れば売れる」という状況だったが、落専務の心の中には「もっと多種類のワインを作りたい」という願望が膨らんでいった。多種多様なワインを作るには多品種のブドウが必要だが、当時の北海道の気候に耐えられるのはドイツ系の品種のみ。さらに叔父のもとを離れて自分なりのワイナリー経営をしてみたいという思いも強くなり、落専務は長野へ移る。

長野は山梨と並んで、日本のワインの一大生産地である。落専務はここである会社からワイナリーの立ち上げを委託され、3年間畑作りやワイン作りに従事する。が、農地面積が狭く、理想とするワイナリー作りには無理がある土地だとわかり、適した土地を探すように。そして見つけたのが新潟・巻町(現在は新潟市に編入)の日本海に近い土地だった。
新潟で立ち上げたワイナリー「カーブ・ドッチ」(オチのワイン蔵の意)は結果的に大成功を収める。ワイナリーはブドウ畑と醸造所はもちろん、レストラン、宿泊施設、ウェディングホールなどを備えた複合施設へと成長。さらに新潟市内にも進出し、複数のレストランやカフェを運営。平均年7万本のワインを生産し、ワイン販売と飲食業で約11億円を売り上げるまでになった。ところが創業当初の手持ち資金は、実はわずか200万円だったという。
手持ち資金の不足が生んだ ワインの木オーナー制度
ワイナリー経営はブドウ栽培からはじまるため、スタートから最低2年は収益がゼロに等しい。しかし畑と苗を調達するには最低でも4,000万円が必要で、資金はまったく足りない状況だった。もちろん金融機関にも通ったが、笑われるばかり。そこで地元の事業家を片っ端から訪ね歩き、「日本では珍しい事業で地域振興にもなる」と力説して回ったという。やがて100万円単位で出資が集まるようになったが、ワイナリー作りにはまだ足りない。そのとき思いついたのが、「ワインの木オーナー制度」だった。
ワイナリーの顧客は言ってみればワイナリーのファンのようなもの。毎年ワインの出来上がりを楽しみにし、自分たちで楽しむ量だけ購入してくれる存在だ。そこで落専務は資金集めと同時に顧客作りに着手。自作のニューズレターを定期刊行し、東京近郊に住む友人知人などへ送るようになる。その制作過程で思いついたのが、ブドウの木1本1本のオーナーになってもらうという発想だった。ブドウの木はすべてナンバリングし、オーナー台帳を作って管理。顧客が訪れたときに成長を見てもらい、毎年ワインを1本プレゼントする。悩んだのは1口あたりの金額と期間。どの程度が妥当なのか測りかねていたとき、たまたま目にしたのが経営コンサルタントの大前研一氏が「平成維新の会」を立ち上げ、広く市民会員を募っているというニュースだった。
「1口1万円で会員を募ったところ、最初の1カ月で数千口集まったそうです。なるほど、1万円は集めやすい金額なのだと気づきました。人に何かを広めるときはシンプルでないと。1人1万円で毎年1本のワインを10年間プレゼントする。これでお客様と10年間つながっていけると考えました」
このアイディアは大当たりし、1年間で3,000人の会員を、つまり3,000万円の資金を集めた。4年後には1万人超の組織になり、ワイナリー経営を支えてくれたという。
こうして国内有数のワイナリーとして成長を遂げた「カーブ・ドッチ」だが、落専務は20年間就いていた社長の座を自ら降り、北海道・余市で4軒目のワイナリー立ち上げに挑戦する。「新潟ではそれなりの評価をいただきましたが、長く続けると飽きも来る。50代を過ぎると、人生が一度きりであることをイヤでも感じるようになるもの。私にできるのはワイナリー作りだけですから、最後に日本でいちばん美しいワイナリーを作ろう。そう考えて再び土地を探しはじめたとき、北海道が候補に挙がりました」
折しも余市がワイン特区に指定され、ワイナリーを増やそうとしていた時期で、余市町長も歓迎してくれたという。余市での事業経営や自身の暮らしでは、イギリスの詩人ワーズワースの詩の一節「Plain living, highthinking」がモットー。「生活は質素に、思考は高邁に」をバランスよく実践している。「64歳で裸一貫から再スタートして6年目。ようやく年産46,000本、売上1億2,000万円に達しました。将来は7~8億円の売上を目指していますが、なんといっても夢は余市をナパバレーのように発展させること。最近、私の弟子も次々にワイナリーを開業しており、少しずつ目標に近づいていることを感じます。尚、現在も鋭意増資中ですので、新規出資を歓迎します」
経営者視点 一覧へ

株式会社OcciGabi Winery(オチガビ ワイナリー)
専務取締役 落 希一郎
1948年、鹿児島県生まれ。小学1年生で北海道へ移住。1966年、東京外国語大学英米科(現・言語文化学部)に入学。1970年、同大学を中退。1976年、西ドイツ国立ワイン学校(当時)卒業。国家資格WEINBAUTECHNIKERを取得。帰国後、北海道と長野でワイン製造事業やワイナリー運営に従事。1992年、新潟県巻町(現・新潟市)にて自らがオーナーとなるワイナリー「カーブ・ドッチ」を設立。2012年、北海道・余市町に「オチガビ ワイナリー」を設立。現在もワイン増産と設備拡張に努める。著書に「僕がワイナリーをつくった理由」(ダイヤモンド社)。

 経営に役立つコラム
経営に役立つコラム