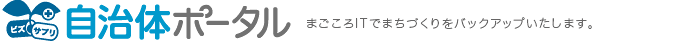
先月、日本経済新聞社が主催する公募文学賞「星新一賞」の選考で、「AI(人工知能)」が書いた小説が1次審査を通過したのをご存知でしょうか。
この「星新一賞」、小松左京・筒井康隆と並んで日本SF界の御三家と称される星新一氏の名前をタイトルにする文学賞だけに、人工知能など人間以外からの応募も可能となっています。
今回、人工知能の作品として応募したのは、公立はこだて未来大学の小説創作ソフト「きまぐれ人工知能プロジェクト 作家ですのよ」が書いた「コンピュータが小説を書く日」、「私の仕事は」2作品と、東京大学大学院の「人狼知能プロジェクト」による、「汝(なんじ)はAIなりや?TYPE-S」「同TYPE-L」2作品の計4作で、どの作品が1次審査を通ったかについては、主催者は明らかにしていません。
「きまぐれ人工知能プロジェクト 作家ですのよ」を例にすると、星新一氏の1000点以上の短編SFを解析して、名詞、形容詞、エピソードなどに分解し、それぞれの要素を「部品」という形にした上で、「いつ」「天気」「何を?」などの「組み立て手順」を「人」が指示する仕組みで作成されています。
作品のごく一部をご紹介します。
『その日は、雲が低く垂れ込めた、どんよりとした日だった。
部屋の中は、いつものように最適な温度と湿度。
洋子さんは、だらしない格好でカウチに座り、
くだらないゲームで時間を潰している。
でも、私には話しかけてこない。』
この文章を見るかぎり、現状では力不足のようにも感じられますが、今後は小説のような創作の分野でも、「AI(人工知能)」の活用範囲は広がっていくのでしょうか。
すでに海外では、記者の代わりに記事を作成している事例もあります。
米国のベンチャー企業オートメーテッド・インサイツ(AUTOMATED INSIGHTS)が開発した「AI(人工知能)」は、1年間で10億本の記事・リポートを作成しています。
この記事自動生成システムでは、ネットの膨大なデータの中から、利用者ごとに好まれる文章の構成や言葉遣いを人口知能に学習させて、あとは「AI」がネット上から必要な要素を選び出し文章化することで、1秒間に2000本の記事を執筆することが可能になっています。
また、身近なところでは、ネット通販での「おすすめ商品」の提示や、顔を「知覚」するデジカメ、「行動計画」を立てるお掃除ロボットなど、既に我々の日常生活の中でも「AI」技術が利用されています。
「人工知能」と聞いて思い浮かぶのは、映画『2001年宇宙の旅』に登場する HAL 9000 のように、人間のよき友人であり、またある時には人類に敵対する存在として、SF作品などに描かれる姿ですが、ここで「AI」の歴史を振り返ってみたいと思います。
「AI(人工知能)」については諸説ありますが、筆者としては第二次世界大戦中、ドイツの暗号機「エニグマ」の暗号解読に従事した、イギリスの数学者「アラン・チューリング」が提唱した「チューリングマシン」の概念が、その後の電子計算機の出現につながり、いま私たちが使っているコンピュータのルーツに相当すると考えています。
なお、「人工知能(Artificial Intelligence)」という用語については、米国の科学者「ジョン・マッカーシー」が1956年のダートマス会議に提出した提案書の中で初めて使用されています。
以降、機械学習アルゴリズムを探求する科学者の様々な活動と、脳の仕組みの解明を目指すイギリスの科学者「ジェフリー・ヒントン」などのニューラルネットワーク研究の潮流が重なり、その後の情報通信技術の進展と相まって、「AI」研究に関してブレイクスルーとなる「ディープラーニング(ニューラルネットワークの多層化)」と呼ばれる概念にたどり着きます。
「ディープラーニング」の概念をひと言で表せば、脳の神経回路を工学的にまねた新しい学習技術で、コンピュータが人間のように「気づき」を得る仕組みを構築するものです。
機械学習は通常「入力データ」と「出力データ」、そして学習するための「モデル(関数やロジック)」で表すことができますが、「ディープラーニング」がこれまでの機械学習と異なる点は、この「モデル」を人間が全て記述しないところにあります。
これまでコンピュータは、人間がプログラムした作業を順に処理してきました。
しかし、「ディープラーニング」の出現によってコンピュータが「自ら学ぶ能力」を獲得したことで、人間にしか成しえない仕事を「AI(人工知能)」が担う可能性が見えてきたのです。
「ディープラーニング」を取り入れた人工知能では、機械学習する際に使われる「変数(特徴量と呼ばれる)」をコンピュータ自らが学習していきます。人間が「特徴量」を設計するのではなく、コンピュータが「特徴量」を獲得し、それをもとに分類・学習することが可能となったことで、これまで人間が介在しなければ到達できない領域に人工知能が近づいたことになります。
単純な言い方をすれば、この「特徴量」は「目の付けどころ」と、言い換えることもできます。過去に「人工知能」と呼ばれていたものは、データの中の「どこに注目」して、「どこに目を付けて」学習するかを人間が決めていました。ところが「ディープラーニング」では、この「目の付けどころ」をコンピュータ自らが決定して学習していきます。
多量のデータを分類・処理することによって、「どこに目を付けて」いけばよいのか、人間の赤ちゃんが学んでいくようにコンピュータ自身が学習するのです。
「ディープラーニング」については、データの質と量(ビッグデータ)が重要な要素であり、それが大量に確保できない場合は良好な結果を導き出すことができないと言われてきました。しかし、それを補完するような形でネット社会が進展し、ネットワーク上に膨大なデータが蓄積され、それを高速に処理する技術を獲得した現代、「AI(人工知能)」は私達のより身近な存在になりつつあります。
その「ディープラーニング」で注目されている技術の1つが、「画像識別」の能力です。人の仕事の中で「認識する」言い換えれば、監視する「見張る」という行為がありますが、街の様々なところに設置されている監視カメラの画像も「ディープラーニング」を活用した新たな展開が期待されています。
この監視する「見張る」という分野では、土砂崩れが起こる、河川が氾濫する、そのような予兆がありそうな時に監視カメラで「見張る」など、災害時の対応に向けた「防災・減災」などの分野で人工知能を活用することで、24時間体制でのモニタリングが可能になるだけでなく、人間が状態監視する場合と比較して、運用コストは飛躍的に減少すると思われます。
この「画像識別」では、人工知能は「画像の認識」、「運動の習熟」、「言語の理解」というステップを踏んで習熟度を高めていきますが、これは人間の子供が成長していく過程に似ていると考えられています。
例えば、車の自動運転では以下4つのレベルに分類されます。
現在は、一般に市販されているものを含めて、レベル1~2の段階です。
しかし今後は、ビッグデータ(地図データ)を解析、自らの行動から運動を習熟し、アルゴリズムの中からルールを自動生成して、推論を導き出すことができれば、レベル4の自動化を達成することになります。
自動運転など、人工知能の分野で世界をリードする「Google」の人工知能研究開発部門、「GoogleX」の創設者、セバスチャン・スラン氏は、10年後の未来をこのように予言しています。
「人工知能は我々の生活や仕事を変え、産業革命と同じような変革をもたらす。
変化することは確実だ。
新たな仕事が生まれ、古い仕事は消える。」
このセバスチャン・スラン氏の予言のように、新たな仕事が生まれて、古い仕事が消えるとすると、我々人間の「仕事」はどのように変化していくのでしょうか?
人間に残された仕事、それは「目的を持って」なにを成すのか、「目的を決める」という最も重要な仕事に集約されると思われます。
人間とコンピュータの大きな違いは、人間は「生命」を持っているという一点につきます。生命体は常に「自分を守りたい」、「子孫を残したい」、「仲間を助けたい」などの目的を持って生きています。生物の進化の過程の中で、そういう目的を持たなかった「種」は滅びました。そして、今残っている我々人間は目的を持って行動しています。
今後、我々人間が仕事をする上で核となるのは「どのような目的」で「なにを成すか」考える「企画力」、行政でいうところの政策を立案して実行する、「政策策定能力」ではないでしょうか。
「ディープラーニング」に関連した動きでは、「Google」や「Facebook」などが数百億円規模の投資を行い、激しい人材獲得合戦を展開しています。またその一方で「人工知能は人類を滅ぼすのではないか」と、宇宙物理学者のスティーブン・ホーキング博士や、実業家のイーロン・マスク氏などが、懸念を表明しています。
人類は、「AI(人工知能)」という名の「パンドラの箱」開けてしまったのでしょうか。テクノロジーは、人間を超える存在を生み出し、人間の仕事を、人類の価値を奪ってしまうのでしょうか。
「人工知能」が開く世界は、夢のようなバラ色の未来でもないし、暗黒の未来でもないと筆者は考えています。
これまでの「人工知能」の研究成果に併せて、「ディープラーニング」の研究がより進展すれば、高い認識能力や予測能力、行動能力、概念獲得能力、言語能力を持つ「人工知能」が誕生し、未知なる領域に到達する可能性もあります。
そして将来、「AI(人工知能)」がベストセラー小説を執筆する日がやって来るのでしょうか。