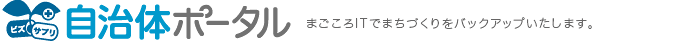
持続可能な「まちづくり」のためには、自治体・企業・市民など多様な担い手が情報や知恵を持ち寄り「共創」することで地域の課題解決を目指すことが必要ですが、ここ近年になり急速な進展を遂げているICTが、その活動をサポートする効果的なツールを提供しつつあります。
既存のICT利活用では、ネットワーク上の情報を共有することで、社会を効率化・活性化することを主な目的としていました。しかし、モノとモノが「IoT(モノのインターネット化)」でつながり、集積されたビッグデータを「AI(人工知能)」が分析することで新たな価値を創造するようになった現在、先端技術の導入によって社会課題を解決しようとする、スマートな街づくり「スマートシティ」実現へ向けた動きが注目されています。
「スマートシティ」について厳密な定義はありませんが、最近の様々な事例を見ると情報通信技術や、それによって蓄積されたデータを活用して、生活の質的向上・社会的課題の解決・経済の活性化などを図る「持続可能な都市」構築へ向けた活動と解釈することができます。
これまでの「スマートシティ」に対する取り組みとしては、一般家庭の家電を含めた都市全体のインフラを情報通信技術によって制御し、エネルギーの需給バランスをコントロールするアメリカの「スマートグリッド構想」や、わが国の「スマートコミュニティ構想」などがあります。世界的なエネルギー事情や気候温暖化等を背景として、エネルギーの効率的利用などの環境保護・保全に重点を置くものが主流で、電力会社・通信事業者等のサプライサイド(供給側)からの技術オリエンテッド(技術起点)の側面が強いものになっていました。
しかし、近年になり情報通信技術が飛躍的に進展したことで、あらゆるモノがインターネットにつながり、リアルタイムで情報・データのやり取りを可能にする「IoT」が普及しました。これにより、エネルギー分野等の限られた領域ではなく、経済・社会の広範な領域で横断的に利活用することで、社会的課題の解決を図り「新たな暮らし価値」を創出しようとする動きが加速しています。
こうした動向の背景には、近年の技術革新によりセンサー等の小型化・省電力化・低価格化が進み、身の回りの家電・製品・機器類など「モノ」と「ヒト」が、スマートフォン・ウエラブル端末などを経由してデータをやり取りする「IoP(Internet of People)」の仕組みがあります。そして「IoT」・「IoP」によって収集されたリアルな現実世界のデータをクラウド上のサイバー空間に蓄積し、そのビッグデータを「AI(人工知能)」を用いて解析・分析することが可能となりました。そこから得られた知識や価値を再び実世界のシステムや製品、サービスなどにフィードバックし改善や高度化などに役立てる、サイバー空間と実世界を融合させる仕組み「CPS(Cyber Physical System)」等の進展を見ることができます。
また、このような仕組みが誕生することで、「スマートシティ」構築のその先には、生産性の向上や運用コストの削減、新たなサービスやビジネスモデルの創出など、広範な分野における経済効果が想定されています。さらに、直接的な経済効果ばかりでなく、生活の質の向上「QoL(Quality of Life)」や健康増進、環境保全など、社会面・環境面において間接的な効果をもたらすことも期待されています。
「スマートシティ」への取り組みが新たな局面を迎えるなかで、重要とされる視点が、そこで暮らす地域住民やその舞台となる地域社会をイノベーション推進の中心に据える「ユーザー・ドリブン・イノベーション」の考え方です。
「ユーザー・ドリブン・インベーション」とは、ユーザーが様々なステークホルダーとともに、新たな技術やサービス・製品開発する場面で、プロトタイプ・実証実験等の試行段階でのレビュー・評価などイノベーションの形成プロセスに能動的に関与することで、より高度なものを目指すユーザー参加型アプローチの総称です。
わが国でも消費者の意見を取り入れるため、メーカー側がユーザーアンケート等を行っています。多くの場合それらは試作品テストなどの開発プロセスの終盤におけるものが多く、ユーザー側の意向が初期段階から組み入れられている事例は少ないのが現状です。また、ユーザーと開発者との間で双方向の情報交換が可能ではなく、多くの場合はユーザーから意見を一方的に聴取することに終始し、ユーザーは受動的な立ち位置に置かれたままになっています。
「ユーザー・ドリブン・イノベーション」のもとでは、アイディアや開発の段階からテスト・改良・製品化の段階まで、ユーザーが直接能動的に関わることを目指しますので、この考え方を「まちづくり」に活かすことができれば、社会的課題の解決や公共サービスの質的向上などに、住民・ユーザー側の意見を直接反映させることが可能になります。
住民の思いを「まちづくり」に活かすための注目すべき動向として、地域住民がICTを活用して地域を改善していく、アメリカ発祥の「シビックテック(CivicTech)」と呼ばれる運動があります。
「シビックテック」とは、市民が自分たちの抱える地域の課題を、テクノロジーを活用して自分たちの力で解決していく手法です。「シビックテック」は2000年代初頭にアメリカで始まり、当初はテクノロジーを活用した行政の効率化に主眼が置かれていましたが、次第に地域の課題解決や資源の共有など「ICT」のちからを得た住民たちが、「自分達の手」で社会・地域を改善していく取り組み全般を表す広い概念になり、いま世界中でムーブメントを起こそうとしています。
この「シビックテック」を下支えするものとして、オバマ政権が政府保有の情報やデータを国民の財産と捉え、これを積極的に開放することで、行政部門の透明性や信頼性を高めると同時に、民間部門でのイノベーションや経済成長・雇用創出を計ろうとした、「オープンガバメント」戦略が挙げています。
これまでの「まちづくり」では、生活インフラに関わる住民サービスの提供者は行政であり、地域住民はサービスの「受け手」でした。しかし近年、ICT関連技術の飛躍的な進歩や普及、行政の持つデータがオープンになる「オープンデータ」の高まりなどにより、地域サービスの担い手が、自治体関係者・事業者・NPO・研究者などによって構成される「民間」の側へと移行しつつあるのです。
「シビックテック」においては、ユーザーである住民側の視点で事業モデルの開発が行われますので、市民の潜在的なニーズをサービスへ反映させることが可能になり、各種行政サービスや公共インフラの利便性・効率性向上など、市民生活の改善につながることが期待されています。そして、「シビックテック」の活動を実体験することで、これまでサービス受給者であった地域住民側に、自分達の地域における社会的課題の解決を「他人ごと」ではなく「自分ごと」と認識して考える環境が醸成されていきます。
具体の事例では、地域内の公共インフラ・施設等の危険や不具合等を発見した場合に、行政と市民で情報を共有し、協働して改善・解決に繋げるイギリスの「Fix My Street」活動や、国内の事例では、千葉市での「ちばレポ」など、すでに一定の成果を挙げているサービスも登場しています。
この「シビックテック」に取り組む地域のプレイヤーは、特殊な技能を持った専門家やIT技術者ではありません。地域の課題を発見しそれを解決するためのアイディアを提案する一般市民や、NPOメンバー、要素技術とアイディアを融合させてビジネスモデルを作り出す地域の事業者等、行政と事業者、大学の研究者など多様な人材によって構成されます。こうした地域に属するマルチセクターの人々が、新たなサービスモデルを企画立案し、メンバーがともに作り手として「協働」し、主体的に地域社会の課題解決に関与することが出来るところが「シビックテック」に取り組む醍醐味なのです。
「シビックテック」が普及・拡大することは、地方自治体の限られた財源・人材のなかで、地域社会が抱える課題の解決に取り組む手法として有用であるばかりでなく、新たなビジネスモデルの創出を通じて、地域経済の持続的成長に繋がる可能性や、その地域に暮らす住民と行政、地元の事業者、NPO、研究機関等の連携を強め、多様なステークホルダーを結びつける役割を果たすことも期待されているのです。
ここまで、「スマートシティ」構想、「シビックテック」運動、「ユーザー・ドリブン」のアプローチなどについて考えてきましたが、わが国政府においても「超スマート社会」の実現を目指す「Society 5.0」を提唱し、先端技術の導入とデータの共有・利活用により、都市ばかりでなく地方も地理的・経済社会的制約から解放されるとしています。
こうした、様々な「まちづくり」に向けた活動を一時的なものにするのではなく、地域社会への参画・協業を持続させるためには、定期的に関係者が集まり、地域の課題を共有し、対話・協業が継続して行われる環境の存在が重要になります。そして、自分達の地域についての課題や問題意識を持つ住民が、その「場」に来ればなんらかの情報を得たり、活動に加わることができる継続的な「場」を形成することが肝要です。単にICT関連技術を活用した利便性の高いビジネスモデルの開発や、生活支援サービスの提供だけを目指すのではなく、地域住民であるユーザー側の視点から絶えず再考していく必要があるのではないでしょうか。