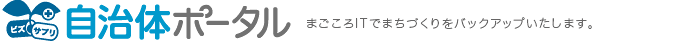
読者の皆さんは高齢化社会についての定義をご存知でしょうか。世界保健機構(以下WHO)では、全人口に占める65歳以上の高齢者の割合が7%を超えた状況を「高齢化社会」、 さらに全人口のうち高齢者の割合が14%を超えると「高齢社会」、高齢者の割合が21%を超えた社会を「超高齢社会」と定義しています。
我が国では、1995年に全人口に占める65歳以上の高齢者の割合が14.6%で「高齢社会」となり、2010年には高齢化率が23.0%で「超高齢社会」へ突入しています。
このような「超高齢社会」の現状を反映するように、最近では「エイジフレンドリー(age friendly)」という言葉をよく耳にするようになりました。この「エイジフレンドリー」ですが、日本では「高齢者にやさしい」と表現されることが多いようです。
この背景には、WHOが提唱する「高齢者にやさしい都市」というコンセプトに基づいた市民参加型の街づくりを進める「エイジフレンドリー・シティーズ(Age friendly Cities)」に対応した動向が見られます。
「高齢者にやさしい」街づくりを進める動きは、今後さらに進展する「超高齢社会」への対応策として歓迎すべきではありますが、その一方で「高齢者にやさしい」1つの局面だけに偏ってしまうことに問題があると思われます。
「高齢者にやさしい都市」というコンセプトの街づくり事例としては、1960年代アメリカ・アリゾナ州に建設された「サンシティ(Sun City)」が最初の例ですが、この「サンシティ」は、入居者の年齢を55歳以上に制限した初の居住コミュニティと言われています。
米国で「サンシティ」が建設された当時、55歳以上の世代の人たちに支持され、その後、全米各地に同様のコミュニティが造成されていきます。しかし、街の建設から30年、40年の歳月の経過とともに居住者の高齢化が進み高齢者ばかりの街になることで、コミュニティの活気が失われていくなど、様々な問題が現われてきました。
日本国内でも1960年代から70年代の高度成長期には、当時20歳代ファミリー層の住宅需要に応えるため「千里ニュータウン」「多摩ニュータウン」など、全国各地に「ニュータウン」と呼ばれる、特定の年代層をターゲットにした公営住宅「団地」が建設されています。
当時、20歳代の家族層に向けて建設された「団地」で最も重視されたのは、夫婦二人と子ども数人で構成されるファミリー層が取得可能な価格設定です。その結果、間取りは、いわゆる「2LDK」の部屋で構成され、4階以上の建物でもエレベーターを完備していない物件が主流になっていきます。
現代の住宅と比較すると部屋には多くの段差があり、間口も狭く、至るところにバリアがあり、かなり狭いように感じられますが、その時代では20代のファミリー層に対して親和性が高い「エイジフレンドリー」な標準的間取りであり、こうした部屋の構成が「団地サイズ」として定着しています。
しかし、入居後40年、50年と時間が経過し住民が高齢化すると、入居当時は「エイジフレンドリー」であった物件が、エレベーターがないため下半身の衰えた年配者には昇降が辛いなど、「団地」建設当時の仕様が高齢化した入居者のニーズと合致しない状況を作り出していきます。
このように「エイジフレンドリー」を標榜しながら、ある時点での時間軸で特定の年齢層をターゲットに最適化された「団地」は、住宅環境の経年劣化と、コミュニティの構成員である入居者の加齢に伴う身体機能の変化などによって親和性の低下を招くことになります。
ここで注意すべき点は、ある時点の時間軸で特定の年齢層に親和性が高いことを意味する「エイジフレンドリー」という概念には、我が国の公営住宅「団地」の高齢化に見られるように「歳月の経過による変化(経年変化)を考慮できていない」というウイークポイントがあることです。
こうしてみると、特定の年齢層に親和性が高い「エイジフレンドリー」という概念ではなく、建物・住宅環境の経年変化や住民の高齢化など、歳月の経過による変化を考慮しながら、各々の世代に対して親和性の高い「ライフサイクルフレンドリー(life cycle friendly)」な発想が「超高齢社会」に必要な概念ではないかと思われます。
内閣府の「平成29年度版高齢社会白書」によると、我が国の総人口は2016年10月1日現在1億2,693万人、総人口に占める65歳以上人口の割合「高齢化率」は27.3%と記載されています。また、アジア各国の高齢化率は2016年現在、香港15.6%、韓国13.6%、台湾12.5%、シンガポール12.3%であり、2030年までにこれらの国が「超高齢社会」に突入すると言われています。
我が国では、幸か不幸か「超高齢社会」における社会的課題が世界のどこの国よりも早く顕在化しています。このような傾向は、世界の国々に先駆けて「超高齢社会」に対応した「ライフサイクルフレンドリー」なビジネスモデルを確立し、いち早く世界市場に投入できる優位性があるとも考えられます。
一方で、我々の身の回りでは情報通信技術が飛躍的に進展し、ネットワーク化された情報サービスは我々の生活基盤になっています。そして、誰もがネットにアクセス可能なスマホを持ち歩き、何時でも何処でも情報を受信・発信することで各個人が多様な価値観を持つ「ミクロ市場が密集した社会」を形成しています。
このような状況を「まちづくり」の観点からみると、自治体の住民情報システム等の各業務が保有するデータや関連情報をビッグデータ化し、庁内横断的なプラットフォーム「住民情報サービス提供基盤」を構築することが重要となります。これにより、医療・介護、予防(健診)に関するデータの分析・解析を行うなど「超高齢社会」に対応した、医療・介護の現状把握や、地域課題の見える化、各種指標のシミュレーションなど、特定の年齢層に依存しない形で地域住民のライフサイクルに適合した、施策の策定・立案に活用することが可能になります。
また、これまでは自治体内部の各業務部門で断片的に管理されていた各種データを、集積・統合化するデータベースシステムを構築することで、そこに蓄積した各種情報を、グラフ・図表、地図情報などとして情報公開することが可能になります。さらに、将来的には「ビッグデータ分析」によって得られた解析データを「オープンデータ」としてWebサイト上に公開するなど、住民に向けた新たな生活支援サービスの創出にもつながっていきます。
これに加え、地域内の事業者や非営利団体等が提供する生活支援サービスの情報や、医療機関・介護施設情報など、地域包括ケアシステムの実現に必要な最新のデータを集約することで、医療・介護サービスの向上と効率化を同時に進めることや、地域の課題解決を加速させることも可能になると思われます。
このように考えると、自治体が保有する情報をビッグデータ化した情報基盤として確立することで、庁内の各部局間のコラボレーションが促進されるだけではなく、データのビジュアライゼーション(視覚化)によって、職員だけでなく住民市民もアクセス可能な環境を作り出します。さらに、データに基づく政策策定や意思決定、効果測定など、自治体の既存業務を変革して事業の質的向上を図ることも期待されます。
スマートシティに向けた「住民情報サービス提供基盤」構築の目的は、住民基本台帳データ(地区ごとの人口及び世帯数)を中心にして、住民生活を取り巻く各分野(環境、防災、交通、観光、医療、福祉等)のデータを集積・分析することで、地域住民が快適に生活できて住み続けたいと思う「まちづくり」を行うことに帰結します。
具体の事例を挙げれば、近隣の自治体と比較して転出率は変わらないが、転入率が低いなど、定住人口の減少や地域内の人口変化に伴う課題への対応。また、確認申請データの活用による建築動向等の把握による地域傾向分析などによって、定住促進施策の展開も可能になると思われます。
古い「団地」の世代構成と居住者ニーズへの対応策としては、多世代居住誘導に向けたシティプロモーションを強化することで、人口バランスを整え全ての世代の住居者ニーズに対応した、多世代居住地域に向けた都市機能の実現にも寄与すると考えられます。
今後、自治体が保有する行政データのビッグデータ化・オープン化に対するニーズは高まるものと思われます。すべての情報を一律にビッグデータ化・オープン化することは困難であっても、住民ニーズに対応した、優先度の高いものから順次データベースの整備に取り組んでいくことが必要であると思われます。
ビッグデータ分析による更なるデータ源の活用や、民間事業者の先駆的な取り組みとの連携強化を図り、地域内での官民学連携によるデータ分析・利活用のベストプラクティスを見出し、ノウハウ等の蓄積を通じて「住民情報サービス提供基盤」の整備を推進する。これによって、新たに創生された「オープンデータ」が再び社会に還元されるような好循環を作り出すことが重要ではないでしょうか。