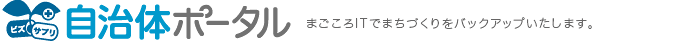
皆さんは、「天円地方(てんえんちほう)」という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。「天円地方」とは、古代中国の道教思想に基づく、天は蓋(かさ)のように「円形」であり、大地は碁盤のように「方形」であると考える、陰陽道の宇宙観です。
私達は普段「地方」という言葉を聞くと、首都や中央に対極するローカルな地域を想像しがちですが、本来の意味はそうではなく、我々を取り巻く自然環境や景観等も含めて、人間社会全般を表現したものだと思われます。
そして、「創生」の意味を辞書で調べると「初めて生み出すこと。初めて作ること」と記載されています。このような観点から「地方創生」という言葉の意味を考えると、我々が自分達の地域でこれまでとは異なる事業を展開する、あるいは他の自治体が実施していない施策を実施する意味と捉えることができます。
我が国における地方行政の新たな取り組みについては、1970年代に流行語となった「地方の時代」に始まり、1980年代以降の「行政改革」の推進など、地方における改革が繰り返し行われてきました。2014年に「日本創成会議」人口減少問題検討分科会が発表した報告書、通称「増田レポート」を発端に「地方創生」というキーワードが一躍注目されるようになります。
「増田レポート」では少子化と人口減少が続けば、20歳代から30歳代の女性人口が2040年までに50%以上減少することで維持困難な自治体「消滅可能性都市」が出現するとのことでした。そして、その中でも人口1万人を下回る自治体を「消滅自治体」と規定するなど、首都圏に過度に集中する人口を経済機能とともに地方へ分散させる必要があると説きました。
しかし冷静に考えると、女性の就業・社会進出が進み暮らしが豊かになり、核家族化が進行すると、子供に掛かる養育費等の教育コストが増加し、それが出生率の低下を招き人口減少につながります。このことは、先進国のライフスタイルに共通する悩みではないでしょうか。
戦後の高度成長期、我々は定年まで一つの企業で働き、地元で持ち家を購入し、地域に根ざすことを理想としてきました。しかし、このような定住を前提とした生活は、終身雇用や男性一人を稼ぎ手とするライフサイクルと結びつき、多様な働き方や家族のあり方を狭め、ひいては経済的停滞を加速させる恐れも内包していました。
1年間で44万人の人口が減少し「一つの中核都市の消滅」に匹敵する規模で人口減少型社会が加速する現実を前にして、地方自治体が「転入人口」を呼び込むため、行政サービスを過度に競い合うようになれば、予算規模が増大し自治体の疲弊を招きます。これは企業が同業他社との価格競争に陥り自滅するのと同じ現象です。
このような「静かなる有事」とも言われる状況の中、「定住人口」「観光人口」に続く第三の人口、「関係人口」が着目されています。「関係人口」とは、過去に居住・勤務などで地域との縁があり、その後も継続的に関係性を保つ人達や、観光で訪れた際にその地域が気に入って、再び来訪する機会の多い観光リピーターなど「観光以上・定住未満」の人々を総称するキーワードです。
「自分達の地域に住み続けたい」「子供や孫にも住んで欲しい」「自分達の地域へ転居をお薦めしたい」と思う、企業でいう「ロイヤルカスタマー」のような住民が存在すれば理想的ですが、そのような住民を一朝一夕で激増させることはできません。そのため「定住」してもらうことを最終目的とせず、自分達の地域に関わる人口づくりに活路を見出す機運が高まっているのです。
「ふるさと納税」制度では、現住所に納めるべき税金を、代わりに地方に還流させる仕組みをつくり出すことで、都市と地方との間に新たな関係性を構築しようと考えました。しかしご存知のように「ふるさと納税」では、他の地域に居住する納税者の歓心を買うため、地方自治体が高額な返礼品を競い合い、高額納税者の獲得競争がヒートアップしています。
世界に目を向けると、システムのオープン化の進展とクラウドサービスの普及によって、様々なシステムが「所有するもの」から「利用するもの」へと変貌を遂げています。そして、サービスの主体は、あくまでもサービスを利用するエンドユーザーであることを前提にした「ユーザー起点」のシステム開発が進められています。
これまで、多くの日本企業ではモノづくりを中心とした「プロダクトアウト」のビジネスモデルが主流で、ユーザー起点で考える市場主導型の「マーケットイン」サービスは少数派でした。しかし、いま欧米などでは、レンタカー、タクシー、バス、電車、飛行機からレンタサイクルまで、さまざまな交通・移動手段を利用者のニーズに合わせてサービスを最適化した「MaaS(Mobility as a Service)」が大きな広がりを見せています。
将来的には複数の事業者が提供する移動手段・サービスを組み合わせることで、社会的リソースをシェアして「共有」する概念へ転換するような、「ユーザー起点」の既存サービスを革新するビジネスモデルが誕生するかもしれません。
「コンパクトシティ」とは、その言葉から連想するとおり「コンパクト」な「まちづくり」を目指す都市政策のひとつです。行政機関、商業施設、学校、医療機関など様々な住民生活に必要な機能を、住民の居住区を地域の中心部に近接させて集約し、地域住民の生活圏をコントロールすることで、無駄のない効率的な住民生活・行政を目指す考え方です。
人口減少が進行する中、今後は高齢者を中心に自然発生的に「ショッピング」や「通院」の際に、利便性の高い市街地エリアへ人口集中することが予想されます。自治体はいま、既存政策の延長線上にある「平成の大合併」のような小規模自治体が「合従連衡」する施策を目指すのか、また「コンパクトシティ」政策を推進するのか、方向性が問われる分岐点に立っているのです。
「コンパクトシティ」では、生活に必要な公共施設や商業地域が集積されて、店舗等へのアクセスが容易になることで利便性が高まり、自動車の利用頻度減少や自家用車を保有しないなど、環境面への貢献も期待されています。
高齢者の生活シーンを考えると、高齢者が電車・バス等の公共交通を利用して行動できる範囲に、利便性の高い施設が集約されていることも重要な要素になります。特に、医療分野の需要の高まりを受けて、限りある医療資源を効率的に利用可能とする地域全体での取り組みが求められているのです。居住地域が一定範囲内に集約されることによって、送迎・訪問介護等の福祉サービスの効率的運用も可能になり、そのメリットは事業者と高齢者の双方にもたらすと考えられます。
いま我が国の地方都市では、以下の状況によって、従来と同等レベルの行政サービスを維持していくことが困難な状況を迎えています。
また、空き家問題、耕作地の放棄、限界集落など、人口減少の影響は非常に大きく、地域の人口が減少することで、今後は多くの社会問題が顕在化することも考えられます。
急速に進む人口減少・少子高齢化を背景とした、社会構造の変化に対応するため、既存の概念に縛られない、斬新な発想に基づく地域社会の活力維持に向けた取り組みが必要なのです。
我々は、高度成長期から連綿と続く既存の発想ではなく、拡大から縮小へ向かって思考を転換する分岐点に立っていると思われます。いま目指すべきはスマートに凝縮しながら、自治体と地域の事業者が連携して、様々な分野の産業を横断するような水平展開型のサービスモデルによる「地方創生」ではないでしょうか。
我が国の政府は「Society5.0(超スマート社会)」へ向かって、すべての関係者が足並みをそろえ、一気に日本のデジタルシフトを前進させることを提唱しています。そして、これからの住民生活を支援する事業モデルには、オープンな連携が不可欠になると思われます。地域住民の様々な生活シーンを下支えし、住民サービスを展開するには地域のステークホルダーが連携することが肝要になります。
これからの施策は自治体と地域の事業者がつながり、生産性向上へ結びつけていくことが必要になります。地域の産業を横断するような、観光、健康医療、環境、エネルギー、農業、移動手段などの各分野を連携させる施策展開に向けて、それを基盤となって支えるプラットフォームのような「地域基盤システム」の構築を目指すべきではないでしょうか。
現在、我が国の政府では第2期となる「地方創生」について議論が進められていますが、「まち・ひと・しごと」の3セットに注目した政策を踏襲しながら、そこに「関係人口」の概念を持ち込み「定住」にこだわらない方向性を打ち出してくると思われます。
いま「観光」は、世界的な戦略領域として認識されています。インバウンドが活況を呈している現在こそ、我々は自分達のエリアにおける地域づくりとは何か、自分達は何を目指しているのかについて再度考える必要があります。そして、その方向性を定め、意識を共有することで地域の振興につなげる仕組みを創り出し、実践することが求められています。
地域が付加価値を獲得するためには、地域以外の人々に自分達の地域を特別な存在として認識してもらう必要があります。強力に地域と顧客とをつなげることができるのが「観光」であり、そこから醸成された「関係人口」の役割は大きいと思われます。
このように考えると、短期的な観光消費の経済効果を狙うことに傾注するのではなく、観光を通じて「関係人口」を獲得し、中長期的な戦略で地域のブランドイメージを向上させ、地域全般の付加価値を高めていくことが必要なのです。
こうした地域づくりは、短期的な観光振興施策を行うのでははく、地域における各分野の産業を横断して自治体と地域の事業者がつながり、地域全体の連携が可能となる「地域基盤システム」のような仕組みを創り出すことが、新たな時代の「地方創生」に求められるのではないでしょうか。