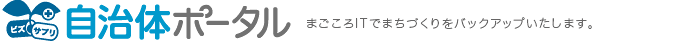
新型コロナウイルスの影響によって、我々の日常生活は劇変した感がありますが「スマートシティ」プロジェクトについても例外ではありません。2020年5月9日、Googleのグループ会社Sidewalk Labsはカナダのトロントでウォーターフロントエリアを「スマートシティ」として再開発する構想「Sidewalk Toronto」からの撤退を表明しました。
「Sidewalk Toronto」プロジェクトとは、開発地区をプラットフォームと位置付け、エネルギー・物流等のインフラ整備、住宅・建築物や街路のデザインなどハード面の整備に加えて、「MaaS」によるリアルタイムな交通調整にいたるまで、全てを統合した効率的に運営するまちづくりを目指しています。
当初の計画では、Googleのカナダ本社を移転することも想定されていました。本社をトロントに移転させることで、世界中から企業や人材が集まりやすい環境を創り出し、これによって経済の活性化を図るだけではなく、住民にとって最適な暮らしを実現しようとしていました。
プロジェクトからの撤退理由として、Sidewalk Labsからは世界的なパンデミックの影響で、過去に例のない経済的に不安定な状態が発生し、計画の中核的な部分を犠牲にせずにプロジェクトの収益性を確保することが困難になったと発表されています。Sidewalk Labと行政・地元住民とが密接に連携するような信頼関係を築きあげる前に、新型コロナウイルスによるパンデミックの影響を受けたことは残念としか言いようがありません。
このGoogle撤退のニュースは、国内外の「スマートシティ」計画に取り組む行政関係者・企業等に大きな衝撃を与え、今後のプロジェクトの進捗に暗い影を落とすのではと懸念する声もあります。しかし、その一方で世界が直面するパンデミックの対抗策として、「スマートシティ」が持つ有用性を再認識しようとする動きも現れています。
「スマートシティ」について、統一された定義はありませんが、極言すれば「大量のセンサーによるビッグデータの取得」と「AIによるアルゴリズム処理」、それを「IoTを通じて実生活にフィードバックする機能」を保有した都市と言えるかもしれません。
米国の調査機関「ABIリサーチ」の2020年3月期レポートでは、新型コロナウイルスの影響で、世界中の都市が「都市の防災力(Urban Resilience)」を高めるための取り組みを優先するようになり、「スマートシティ」の原動力となる「AI×データ」利活用が進展する可能性が高まると言及しています。
そこで、重要になるのが「データの取得」です。データがなければAIのアルゴリズムは成長することができません。そして、データを取得するためには大量のセンサーが必要になります。つまり、「スマートシティ」においては、身の回りのあらゆる「モノ」がセンサーと「IoT」でつながり、都市内の様々な事象がデータ化される社会環境の実現が前提になります。
また、感染症予防の観点から見ると、都市内における地域住民の「移動履歴」や「接触履歴」、SNS等に書き込んだ情報など、都市内のデータを収集・分析することで、感染ルートや感染クラスタの特定・隔離を迅速に行うことが可能になります。これによってパンデミック拡大を防止するための有効な手段になると思われます。
私たちを取り巻く様々な「モノ」が「IoT」によってつながる、「スマートシティ」が実現するまで、いましばらくの時間が必要と思われます。しかし、我々が日常持ち歩いているデバイス「スマートフォン」をセンサーと見なすことで、そこから得たデータを利活用できる環境を我々は既に手に入れています。
いま、注目されているスマホアプリとして、ユーザー同士の接触記録を確認し、感染者と接触した人を探し出す「接触確認アプリCOCOA)」があります。また、QRコードを利用してイベント・会議等の参加者名簿を作成し、感染者と接触した人を探し出す「大阪コロナ追跡システム」などの「濃厚接触追跡アプリ」もあります。
どちらのシステムもBluetooth通信によって、お互いのスマホが一定の範囲内に同アプリの利用者がいることを認識し、利用者同士が近接して数分以上同じ場所に留まれば、両者の「スマートフォン」内部に固有の識別コードが生成されます。
そして、両者が「接触」した記録を残すことで、新型コロナウイルスに感染したと診断された場合、アプリを通じて報告すると、直近二週間以内に接触した他の登録ユーザーに、感染拡大を防ぐためのアドバイスが送信される仕組みになっています。
この「濃厚接触追跡アプリ」の事例のように、まずは既存プラットフォームの延長線上で新たな施策展開を目指す、いわゆる「レトロフィット型」のプロジェクトから始めることが、「スマートシティ」実現への近道ではないでしょうか。
「ポストコロナ時代」には、リモート環境による働き方がグローバルに定着すると思われます。そこで、次に目指すべきは、ネットワーク上のサイバー空間で「リアルシティ」と同期して存在する「サイバーシティ」の構築です。
「サイバーシティ」が保有する機能は、感染症対策や災害発生時などの緊急時に活用されるだけではなく、常に「リアルシティ」と同期して存在し、「リアル」都市と「サイバー」都市が互いに補完し合うことで、生産性の向上や働き方改革に寄与することが可能になります。
「スマートシティ」の本質は、データを多面的に活用することで都市が持つ課題を解決し、住民の生活シーンに寄り添ったサービスを提供することではないでしょうか。このように考えると、一から都市のハードを作り上げる「フルスクラッチ型」の施策ではなく、いま検討すべきは、スピード感を持って取り組むことが可能な、「レトロフィット型」の「5G」等を利活用した通信インフラによるサービス創生なのかもしれません。
これまでの経過を振り返ると、我が国では2019 年にデジタル手続法が成立し、「行政サービスの100%デジタル化」が目標とされていました。しかしその反面で、過去の大規模災害の発生時には、情報のデジタルデータ化や行政手続きのオンライン化の必要性が強く認識されるばかりで、過去の教訓を活かすことができていないのが現状です。
世界的なパンデミックの影響によって、世界の各国でデジタルガバメントへの取り組みが急速に進展しています。その中で、我が国においても従来の組織体制や業務プロセスの改革が成されなければ、官民ともに機能不全にいたるのではないかと危惧する声が上がっています。また、これに加えて、デジタル技術を有効に活用することで、緊急時においても行政機能の維持や様々な対処方法の考案・実装が可能になることも期待されています。
「情報・データ」の収集はデジタルガバメントの基盤と言えますが、今回の新型コロナ危機では、政策の意思決定や国民の理解に必要な「情報・データ」を収集し活用する仕組みが、未成熟であることも明らかになりました。
今回のパンデミックを契機と捉え、各種報告や情報収集プロセスの抜本的な見直しを行い、円滑なデータの共有や分析が可能となるように、電子的なデータフォーマットの標準化等を推進することが必要ではないでしょうか。
今回の新型コロナ危機では、人と人との接触が新型コロナウイルスの感染を拡大させることが明らかになり、感染者・医療従事者・その家族など、人々の安全を確保するために、関連情報をどのように公開・共有するのか、個人のプライバシーと公益のバランスをいかに確保するかが問われていると考えられます。
我が国のマイナンバー制度には、国民生活を支える社会基盤となるほか、行政のデジタル化を推進する基盤としての側面があります。マイナンバー制度等の「デジタルID」の利用を促進することによって、公的個人認証システムを活用したオンライン上での個人識別、本人認証、電子決済等を、より簡便・安全に行うことが可能になります。
大規模災害の発生や、今回のパンデミック発生のような緊急時においても、「デジタルID」による個人認証の仕組みを有効に活用することができれば、給付金等の迅速な対応や、各種届出や申請手続きに要する人的負担を軽減できると考えられます。
そして、更に推進するべきは「デジタルID」を活用した、プッシュ型サービスの実現ではないでしょうか。必要な人に必要なサービスを迅速に届けるためには、マイナンバー制度で対象者を特定できるシステムを構築し、給付金の自動振り込みを可能とするなど、プッシュ型サービスの実現が必要になります。
このような新たな施策の推進には、法制度の改正やシステムの改修、業務体制の見直し等も必要なため、短期的な解決は難しいと思われます。しかし、今回のようなパンデミック発生や災害発生時などの緊急時においても、手続きがネットワーク上で完結することのメリットは大きく、いまこそ真剣に議論すべき時だと思います。
「スマートシティ」の実現に向けて、最大の課題は「デジタルID」など、個人情報と密接に関連したデータを、個人の権利を侵害することなく管理する枠組みをどのように構築するかですが、「スマートシティ」に暮らす全ての都市生活者が、恩恵を受けることができる、都市の在り方と暮らし方の根本的な改変が必要なのです。
パンデミックが現実となった世界において、「スマートシティ」の有用性はより明確になったと考えられます。ポストコロナ時代における、行政のデジタル化への取り組みは、行政内部のデジタル革新とともに、市民や民間セクターとの関係性を見直す好機であると思われます。
我々が今回の体験を未来に向けて活かすためにも、新たな時代において、自分が暮らす社会の仕組みや在り方について再考するべき時期が来ているのではないでしょうか。