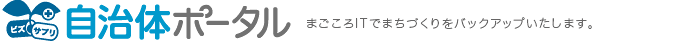
いまコロナ禍のなかで、「レジリエンス」という言葉が注目されています。「レジリエンス」とは主に心理学や生態学で用いられる用語で、外的なショックにも倒れることなく、元に戻る復元力の強さを意味しています。それが人の生業であるビジネスの分野にも使われるようになり、「不確実性に対応できる適応力」と捉えられるようになりました。
今後、我々には自然災害等の発生による突発的危機への対応や、人口減少・少子高齢化に伴う社会的変化による慢性的危機に対して、それらの危機を「予防・軽減」させながら立ち向かっていく「危機対応力」や、復興を超えて更なる発展を図るための「創造的再生力」が求められているのかもしれません。
「2025年の崖」というキーワードとともに、もし「DX」が実現されなければ、2025年以降、年間12兆円の経済損失が生じる可能性があると指摘して、注目を浴びた「DXレポート」が発表されてから既に三年が経過しています。しかし2025年を迎えるまでもなく、我々は新型コロナウイルスの感染症拡大によって、デジタル化を前提に変わらざるを得ない状況に追い込まれています。
「DX(Digital Transformation)」の本質は、デジタルではなくトランスフォーム「変わる」ことにあると思われます。今後発生するかもしれない、自然災害や新たなウイルス出現の脅威などの、様々な環境変化に柔軟に対応するためには、今回の新型コロナウイルス感染拡大の危機を「DX」を推進することで、新たな仕組みを構築するチャンスと捉えるべきなのかもしれません。
いまなぜ、日本において「DX」が叫ばれているのか。人口減による人手不足の問題や、持続可能な社会作りが急がれるなかで、新型コロナウイルスによる感染症が蔓延し、効率よく課題を解決する手法として「DX」に注目が集まっています。デジタル化は手段であり、目的ではないことを認識することが重要なポイントです。
一方で課題となっているのはデータの利活用です。「DX」を進める上でデータとAIが大きなカギを握っていますが、分野を越えて連携・リンクしていく仕組みが盤石とは言えない状況にあります。特にデジタル社会の「石油」とも呼ばれている、データの取り扱いについては、これから「DX」を推し進めていくためには、どのようにデータを保管・管理し活用するのか考える必要があります。
社会のデジタル化に伴い、データは智恵・価値・競争力の源泉となります。そして、データは単に存在すれば良いのではなく、大量の信頼できるデータが互いに連携することで、新たな価値を創出して社会のニーズに応えることが求められています。
今回の新型コロナウイルス感染拡大の危機では、国・自治体・医療機関等の間で情報共有が進まないことや、データの構造化・標準化が不十分で、データを活用した感染症対策関連サービス提供等の迅速かつ的確な対応が困難になるなど、多くの課題が指摘されています。
これはデータを活用する意識が希薄であり、それぞれのシステムが各業務に閉じたかたちで管理され、データ活用の基盤となる、デジタルデータの整備、標準化、取り扱いルール等が脆弱であることに起因していると思われます。
地方自治体等の行政機関は、「最大のデータホルダー」であり、その施策展開が社会全体に大きな影響を及ぼす「プラットフォーマー」とも言えます。「DX」の推進を行政のデジタル化に留めるのではなく、民間と連携協調することで民間の「DX」への取り組みを促し、データ利活用の高度化に寄与すべきではないでしょうか。
新たな価値を創出するためには、「現実の空間(フィジカル空間)」と「仮想空間(サイバー空間)」を高度に融合させた「デジタルツイン」を前提に、国全体のリエンジニアリングを行い、サイバー空間上に国家・社会を再構築することで、経済発展と社会課題解決の両立を目指す、データの幅広い活用を促進する必要があると考えられます。
そしていま、住民生活を下支えする基礎データ「ベース・レジストリ」が注目されています。住民基本台帳、法人登記簿、不動産登記簿など、社会の基盤となる基本データ「ベース・レジストリ」ですが、「ワンスオンリー」を目指したサービスを展開するためには、これらのデータが構造化され、正確でアップデートされた環境を構築する、データ戦略が必要になると思われます。
「電子国家」として世界の最先端を走る、バルト三国のひとつ「エストニア」では、「e-government」と呼ばれる国民データベースによって、行政手続きの99%がデジタル化され、オフラインでの手続きが必要なのは「結婚」「離婚」「不動産売却」のみになっています。
日本のマイナンバーカードに相当する、IDカード「eIDカード」は保有が義務付けられ、ほぼ全ての国民が所有しているため、行政手続きだけではなく、銀行や学校、民間企業による各種サービスにおいても日常的に利用されています。
「エストニア」では、2001年に各種組織・機関の分散されたデータベースを「暗号化ハッシュ関数」を利用することで安全に連携させるプラットフォーム「X-Road」を構築しています。これによって、651の機関と企業、504の公的機関、さらに2,691の異なるサービスが連携可能になり、いまでは、アゼルバイジャン・フィンランド・ウクライナ・モーリシャス・ナミビアなどの国でも導入が進んでいます。
「エストニア」のデジタルID制度のデータ管理では、中央に全てを集めて管理するのではなく、例えば「住民登録」「健康保障登録」「自動車登録」「銀行」など、データベースごとに管理するデータを「x-Road」によって連携させています。これにより、必要な人が必要に応じて必要なデータベースだけを、高速・安全に取り出すことができる、シームレスな連携を可能にしています。
人口約132万人、面積は日本の約9分の1程度の小国「エストニア」が、なぜ世界でもトップレベルの「電子国家」になり得たのでしょうか。かつては、デンマーク、ドイツ騎士団、スウェーデン、ロシア帝国、そしてソ連と次々に支配者が変わった歴史から、物理的に国が奪われたとしても、オンライン上で電子的に国をデータとして保管しておくことで国民を守り、国と民族を永続させるための戦略が根本にあると思われます。
電子国家としての「エストニア」の戦略は、単にテクノロジーによって生活の利便性を向上させるだけでなく、自分たちの歴史や生活、そして自由を守るためのものと思われます。国家という中央集権的な組織が、分散されたデータベースを連携させる非中央集権的な仕組みを重要視する姿勢は、新たな時代の国家のあり方として、注目に価する戦略ではないでしょうか。
自治体における「DX」推進に関しては、「デジタル化が目的ではなく、地域課題を解決するための手段であること」、そして「組織や考え方を変革して、これまでとは異なる価値観を生み出し、それが真の意味で住民のための事業展開であり、サービスモデルになること」を理解してもらうことが大切です。
これまでのデジタル化の歩みを振り返ると、全ての始まりは1995年前後のインターネットが爆発的に普及した「ネット革命」ではないでしょうか。そして、それが2001年のe-Japan戦略で「IT革命」と称した政策につながっていきます。
しかし、残念なことに21世紀を迎えた途端、世界的なネットバブルの崩壊とともに、経済の大スランプ期「失われた20年」のど真ん中で、日本のデジタル革命の波は途絶えてしまいます。
これまでの経過を考えると、いまこそ本気で「DX」に取り組む時ではないでしょうか。言い古された言葉かもしれませんが、いま世界で起こっているデジタル革命は、かつての産業革命に匹敵する大変革です。行政の「DX」が進展すれば、行政とのやり取りが必要な民間業務等がデジタル化され、我が国の「DX」に向けたムーブメントが加速すると思われます。
世界に目を向ければ、「エストニア」のように国家戦略としてデジタル化に邁進する国家が現れています。いま、このデジタル化の流れをキャッチアップできず、潮流に乗り遅れることで、先進諸国の後塵を拝することは避けたいと考えるのは私だけでしょうか。
「エストニア」の様々な情報をデータベースで一元管理し、あらゆる分野で活用する取り組みは印象的で、日本のマイナンバーカードに相当する「eIDカード」の保有を義務付けるなど、我々のメンタリティーには馴染まないと感じますが、学ぶべき点も多いと思われます。
極端に言えば、「エストニア」の電子立国の戦略は、ハードウェアの「国土」と、ソフトウェアの「国家OS」を使用し、データをネットワーク上に保管するシステムと言い換えることができます。
この仕組みであれば、戦火によって一時的に国土が失われたとしても、新たな国土で「国家OS」を再起動させ、ネットワーク上のデータとリンクさせれば、新たな国家を再興することが可能になります。
「2025年の崖」に到達する前に、新型コロナウイルスの感染症拡大による「2020年の崖」が出現しましたが、いまこそ我々も考え方を変容させ、時代に即応した文化・システムを受け入れる「マインドセット」に変換する時期を迎えているのではないでしょうか。