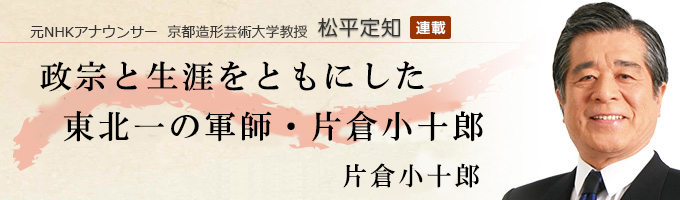以下は、いずれも、歴史上は政宗のパフォーマンスと喧伝されてきた二つの出来事だが、私は、その「作・演出」は、二つとも片倉小十郎だったとみる。
一つは、秀吉の小田原・北条攻めの際の、政宗の参戦大遅刻事件である。
秀吉が四国、九州を平定し、次のターゲットを関東に絞り、小田原の北条潰しに向かったのは天正18年(1590)3月1日。この時、参加要請を受けた政宗は、「参戦すれば、『私戦禁止の関白命令』を無視して、摺上原で蘆名氏と『私戦』したことも、その戦に勝って獲得した会津の地も、両方、目をつぶってやろう」という秀吉の好条件の要請にも、すぐには従わなかった。彼には彼で「北条と組んで、秀吉に対抗して関東支配を…」という思いが、心のどこかにあったからである。
側近・小十郎の「いま、秀吉を敵に回しても全く勝ち目はありません」という必死の忠告を受け入れ、参戦を決めたのは要請状が着いて1週間以上もあとのことだった。しかも、小田原への出立準備さなかの4月5日、実母による政宗毒殺未遂事件が起こり、その後処理の問題もあって、実際の参戦は6月にずれ込むのである。この時、戦いの趨勢はほぼ決していた。「何をいまさら!」と秀吉の怒りはすさまじい。政宗が詫びを言おうにも会ってもくれない。政宗は箱根山中で謹慎の日々を余儀なくされる。
そして、やっと迎えた謁見の日の6月9日。片倉小十郎は考える。「これは、尋常な手段ではイカンな」―――秀吉の前に現れた政宗は、髷を落としたざんばら髪である。甲冑の上には白の陣羽織を羽織った死装束!!「政宗、本日は、死を覚悟しておりまするッ」。一瞬、息を呑んだ秀吉だったが、すぐに平静に戻った。秀吉は席を立って政宗に近づくと政宗の首のあたりを持っていた扇で叩き、「もう少し遅かったらここが危なかったのう」と言って、笑ったという。度肝を抜くパフォーマンスが嫌いではない秀吉の性格を計算して、小十郎が考案し、政宗が実行に移したプレゼンテーションだった。恭順の意をビジュアル化して見せた小十郎の演出。勿論その裏には、「今後の政局運営を思えば、秀吉は、位置的に、巨敵・家康の背後にいる政宗をそう簡単には殺せまい」という確かな読みもあったのであるが。
二つ目は、それから8ヶ月後。場所は京都の都大路。金箔の磔柱を先頭にした行列が静やかに進み、その後ろの馬上に政宗がいる。またしても、白装束である。「政宗ほどの人物が磔刑になるのなら、その柱は金色こそが相応しい」―――そんな意思表示である。これは奥羽で発生した大規模な一揆を裏で操っていたのが政宗、という疑惑が持たれたためのパフォーマンスだった。その証拠として、密告者は「一揆を扇動する政宗の花押入りの檄文」を、動かぬ証拠として秀吉側に提出したのだった。政宗には、中央の思い通りにはさせない、という意思が皆無だったわけではないけれど、でも、まあこれはあくまでも、一地方の案件処理の手立ての一つという思いでその種の紙片を確かに出してはいるのだ。しかし、日本国内が、秀吉のもとで全国的にまとまり始めたこの時期に、局地的であるにせよ、争いを煽るような紙片はまずいと判断した小十郎は、今回は知らぬ存ぜぬを貫くのが肝要と考えた。そこで彼は、また、驚くべき手段を講じるのである。
政宗の花押は、鶺鴒を意匠化したものだったが、小十郎は政宗に、秀吉に見せる文書の花押に、あらかじめ、その鶺鴒の目に針の穴を開けておくことを提案した。小十郎の指示に従った政宗は、小十郎とともに上京。そして、都大路での、あの金色磔柱行進の数日後に行われた秀吉のもとでの事情聴取の折、花押付きの文書を手にかざしながら、こう説明する。「秀吉様の目の前にある紙片は、私のものではございませぬ。私がいま手にしております本物には、鶺鴒の目の部分に小さな穴があいてございますが、如何でございましょう。」―――差し出した政宗の手紙や文書には、花押の鶺鴒の目の部分には悉く小さな穴があいている。秀吉の持つ書面の花押の鶺鴒の目に、穴はない。秀吉は、内心はともかく、今回も、苦笑いをしながら政宗を赦した。
その秀吉の目の先は、「また、こいつか」と、片倉小十郎を捉えていたに違いない。秀吉は、こうした「業績」を見て、この小十郎を5万石という、それまでの10倍の禄を提示して、直々にヘッドハンティングしようとしたことがある。その時の小十郎は「私の主君は政宗公一人でございますれば…」と、辞去したという(名将言行録)。

片倉家御廟所
家族運に恵まれなかった政宗(父・輝宗は、敵に捕らえられ、政宗軍の銃砲の盾にさせられたが、その時、父の『俺に構わず撃て』の声に目を瞑って引き金を引いて殺してしまったし、母・義姫には政宗は毒殺されそうになった。弟・小次郎は後継争いで暗殺してしまった)にとって、片倉小十郎は「肉親以上」の存在だった。
信長・秀吉・家康とは30ほど年若い政宗は、歴史上、よく「遅れて来た天下人」と言われるが、本人は一度も「遅れてきた」とは思ってはいなかったのではないか。機会が来たらいつでも天下を!と思い続けていたと思う。政宗は小十郎亡き後20年近くを生きるが、その間、メキシコ・スペインの経済力を借りて日本に風穴を開けようとした。ローマとも仲良くしようとした。こうした企ては支倉常長特使の尽力むなしく失敗に終わり、これ以後、政宗はすっぱりと政治向きの話から「引退」するが、それにしても、外国勢力を利用して日本に新風をという政宗の融通無碍の発想は、彼岸の小十郎にはどう映ったか。
私には、満足気に首肯する稀代の軍師の姿が目に浮かぶのだが。
 著名人から学ぶリーダーシップ著名人の実践経験から経営の栄養と刺激を補給
著名人から学ぶリーダーシップ著名人の実践経験から経営の栄養と刺激を補給