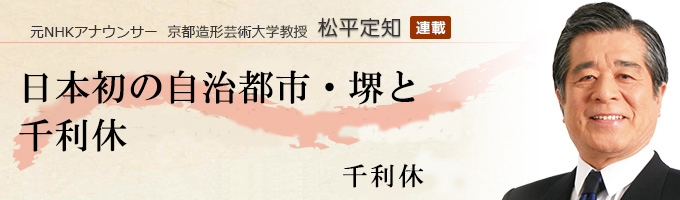田中与四郎という人物がいる。父の名は与兵衛。与兵衛は大坂・堺で魚問屋を営んでいた。魚問屋だから、扱う商品は、魚以外にも貝や昆布など多岐に亘る。だから、それらを保管する倉庫(納屋)もいくつか持っていた。大阪・堺といえば明や南蛮との貿易で栄えた一大港湾都市。その町で、与兵衛はその魚問屋と貸倉庫業で財を成した。だから息子の田中与四郎は、その大都市に住む金持ちのボンボンということになる―――と言っても、そもそも、その「田中与四郎って誰?」って話だが、この与四郎こそが、千利休である。
尤も、この「利休」という名はずっと後年の、天正13年(1585)の9月、彼64歳の時に正親町天皇から賜ったもので、生涯5年半しか使っていない。彼は17歳の時に茶の湯の道に入るのだが、そこで半世紀近く(45年間)は、「宗易」を名乗った。利休は大永2年(1522)生まれ。彼の干支一回り下に信長がいる。秀吉は生年不詳だが、信長の3,4年後に生まれた、といわれている。家康はそのあとの1543年生まれ。この年は種子島に鉄砲が伝わった。日本はこの年、初めて、「ヨーロッパ」と接点を持つ。利休は「そんな時代」に生きた。
フロイスは「堺は日本のヴェネチア」と言った。ヴェネチアは、当時イタリアで栄えていた都市国家で、海外貿易で儲けた商人たちが武装して独立を守っていた自治都市だった。翻って日本。当時は群雄割拠の戦国時代だった。とびぬけた実力を持つ指導者がいなかったため、堺も、自分たちの力で町の周囲に濠を巡らせたり、塀を建てたりして、他所とのけじめをつけた。自分たちの金で浪人を集めて武装集団を作り、他所からの侵入に備えた。この日本最初の自治都市・堺は、大名の庇護を受けず、だから税金も納めなかった。堺の商人は、海外との貿易の影響もあり、「独自の文化」の大切さを痛感していた。やがて彼らは、独自の美意識で「茶の湯」という文化を生み出していく。利休と茶の湯の出会いも、堺の金持ちのボンボンとして、その必須科目履修といった感覚だったのかもしれない。

この、「茶の湯」の持つ特異性に興味を示した男がいた。信長である。信長はそれまでの群雄割拠の戦国時代を切り裂いて突如登場した革命児だった。古い常識には囚われない発想と、鉄砲の有効利用など機動性に富んだ大兵力で、次々に強敵を倒していった。茶の湯、茶道具、茶器―――『これを「政治」に利用できないか』と信長は考える。茶会は情報収集の恰好の場となるし、茶器は家臣への何よりの褒美になる。家臣に、戦功のたびに領土をくれてやるといったこれまでの方式では、国土の広さに限度がある現実ではいずれ行詰まると信長は、かねがね思っていた。彼が天下取りレースで一頭地を抜いたのが永禄3年(1560)の桶狭間の戦いだった。当時、天下に最も近いと言われていた大重鎮の今川義元相手に、まさかまさかの勝利をあげたのは、信長、26,7歳の時。その信長は8年後には京都に上り、近畿一円を支配下におさめた。天下統一を目指す信長は、堺の富に目を付けた。軍事費を出せと命じたのである。堺の「ウリ」は「自治・独立の自由都市」だったが、堺衆が傭っている浪人兵とは桁違いの信長の「軍の力」の前に、堺は、その「ウリ」を捨てた。堺は、天下統一目前の信長の支配の下で生き残る、という道を選ぶ。堺の豪商は信長に金銭を提供し、優れた茶器を献上した。利休はそうした豪商の一人の茶人・今井宗久(信長の茶会を取り仕切る茶頭)と親しかったので、その宗久を通して信長に「お目通り」が叶った。茶の嗜みもある信長は、一目見て利休の力量を見抜き、彼を3000石という破格の待遇で召し抱え、茶頭に抜擢する。信長の家臣たちは、信長から茶会に招かれたり茶器を拝領したりすることは大きな名誉であったから、その茶会を取り仕切る利休は憧憬の対象だった。そうした家臣の一人に秀吉がいた。そして、その秀吉に興味を持ったのが利休だった。利休の、茶器に対して見られる優れた審美眼鑑識眼は、「信長の次(の日本)は秀吉」と見ていた。
 著名人から学ぶリーダーシップ著名人の実践経験から経営の栄養と刺激を補給
著名人から学ぶリーダーシップ著名人の実践経験から経営の栄養と刺激を補給