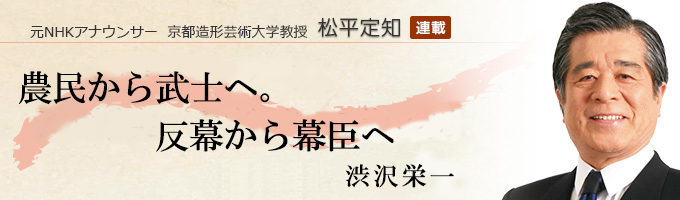前号の掉尾に記した平岡円四郎。そもそもの出会いは、栄一が22歳の頃でした。その5年程前、栄一は故郷の役人の理不尽な態度に、「武士になって、幕府を倒す」と攘夷思想にのめりこんでいった経緯は前号で触れました。そんな彼が、いつも一緒の仲良しの2歳違いの従兄・喜作と江戸に出て千葉道場に出入りし、攘夷の志士たちとの人脈を広げようとしていたころ、栄一と円四郎は初めて会ったのです。円四郎は水戸藩主・徳川斉昭の7男・将軍後継職・一橋慶喜の側近(用人)でした。かたや攘夷の志士、かたや幕臣。お互い立場はまるで違うのに、この二人、初対面の時からなぜかお互い、ウマが合いました。
後年、栄一は、その著「実験論語処世談」の中で円四郎のことを「一を聞いて十を知るという質で、客が来るとその顔色を見ただけで、彼が何の用事できたか、ちゃんと察するほどのものであった」と記しています。一橋家は田安、清水と並んで御三卿といわれ、尾張、紀州、水戸の御三家同様、将軍の跡継ぎを出す資格のある家格でした。でも、家臣団は御三家とは違って、自前の家臣ばかりではなかったのです。
安藤優一郎氏の「幕末の志士渋沢栄一」によりますと、御三卿の家臣団は「幕府から出向してきた幕臣の次男三男で主に構成され、家老や用人などの上級役職も出向の幕臣で占められることもしばしば」だったといいます。とりわけ一橋家は当主の慶喜が将軍後継職として幕府首脳部の一角を占め、その政治的立場が上昇を続けていたため、用人として一橋家を切り盛りしていた平岡には優秀な家臣を一人でも多く抱える必要があったのでした。
そんな平岡の肚に、栄一の反幕の立場以外は̶̶̶才気、熱誠、行動力が瞬時に届いたとしか言いようのない出会いでした。栄一は初対面の時から一橋家への仕官を強く勧められますが、その時は、攘夷の志士として、前号で触れた、「高崎城乗っ取り、横浜外国人居留地焼き討ち事件」を計画中でしたから、首肯することはありませんでした。でも、現実主義者の栄一は、以後、一橋家への出入りは頻繁にしました。攘夷のための挙兵を完遂するためには、そうしている方が幕府の嫌疑を避けることができる、と考えたからです。
そうこうしているうちに慶喜は京都に行くことになり、用人・平岡円四郎は当然同行します。円四郎は「一緒に行くか?」と栄一を誘いますが、栄一はその好意には感謝しつつ、「反幕の自分」の心の整理がつかず、断ります。でも、栄一はその時、「今回は同行できないけれど、あとで行くことになるかもしれぬので、私に『幕府用人・平岡円四郎の家来の肩書』を頂けないだろうか」と頼み込みます。「こいつ!」と思った円四郎でしたが、もともと栄一を仕官させるつもりでしたから、結局はその申し出を快諾し、自分の留守中でも栄一が訪ねてきたら、それを渡すようにと妻に言い聞かせて、慶喜に従いて京都に向かいました。
やがて、栄一と喜作の二人は故郷を出て、水戸、江戸経由で京都に向かいますが、前号の終わり部分で、彼らが江戸で円四郎の留守宅にわざわざ寄った、と言ったのは、この「円四郎の家来」の肩書を留守居の円四郎の妻から受けとるためでした。留守を守っていた円四郎の妻は、「主人から聞いております」と言って「円四郎の家来」の肩書を渡してくれました。それを手にして、意気揚々と京に上る栄一。おかげで、道中は、役人の苛烈な取り調べを受けることもなく、安穏な旅だったのですが、これなどは現実主義者栄一の面目躍如、といったところでしょうか。
ある日、栄一の攘夷仲間が刃傷沙汰を起こし、その男と手紙のやり取りをしていた栄一は円四郎の家で、幕府役人の事情聴取をうけました。これも円四郎のとりなしで大きな問題にならずに済んだのですが、この時、円四郎は栄一と喜作を書斎に呼んでかなり突っ込んだ話をしています。
「君たちは今、攘夷という立場で頑張っているが、国家の為と一命を擲っても、それが必ずしも国家のためになるのかは、私は疑問である。それより英明な慶喜公に仕えて活動する方が、よっぽど国のためになる場合もある。反幕、倒幕を遮二無二叫んでいる熱誠溢れる攘夷活動家の君たちよ、この際、少し冷静になってみては如何」
 著名人から学ぶリーダーシップ著名人の実践経験から経営の栄養と刺激を補給
著名人から学ぶリーダーシップ著名人の実践経験から経営の栄養と刺激を補給