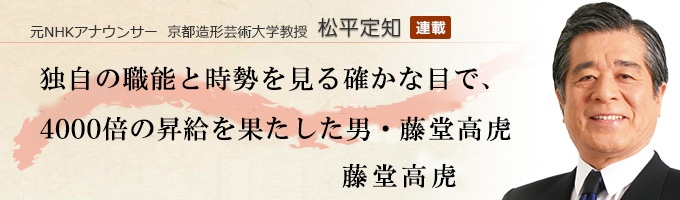「出世」―――それは「働く者」の大きな目標の一つだが、何もそれは現代社会に限られたものではない。時は戦国。ここに、「出世の達人」がいた。彼は、あの時代、金も地位も、コネもないゼロの状態から、末は伊勢一国を統括する大大名にまで上り詰めた。地位も上がったが、俸禄も上がった。彼の75年の生涯、その最晩年に彼が手にした収入は32万石だった。「ただ働き」を何年かしたあと、やっと手にした給料は80石だったことを考えると、そこからでも、実に「4000倍」である。
メジャー通算3000本安打達成のイチローと比較すると、彼がドラフト4位でオリックス球団に入団した1991年、年俸は430万円(推定)だった。最高額はマリナーズ時代の2008年に交わした5年契約で推定9000万ドル。単純に5で割って年俸1800万ドル。計算しやすいように1ドル100円で計算すると18億円。それでも、初任給の400倍ちょっとである。ところがこの男の場合は、その「世界のイチロー」の、更に10倍だったのだ!
その男の名は、藤堂高虎。
藤堂高虎は弘治2年(1556)、近江の小さな土豪の次男に生まれた。父の時代、藤堂家は「地侍」という境遇だった。父の果たせなかった「知行(俸禄)とりの侍」になってみせる―――それが幼いころからの高虎の夢だった。彼は元気で大きな赤ちゃんだった。長じては、190センチ、100キロの巨躯を誇った。この抜群の体力も日本一の昇給率男に成長する原動力の一つだったろうが、彼にはその理由がもう一つあった。それは、「士たるもの二君に仕えず」という武士道精神真只中のあの時期に、生涯10人も主君を変えたその「生き方」だった。彼が選んだのは、いずれも時の権力者、もしくは権力に近い人たち。その「嗅覚」は見事と言っていい。
彼は主君を代えるごとに身上を増やしていく。これを、権力好きの欲の権化と評するのは易しい。しかし、同時にそんな彼を、乱世に生きる術を知っている「生き方のプロ」と評することもできるのである。
彼は「そう生きていけるため」の努力を惜しまなかった。「自分だけの職能」を模索し、研磨した。それは、後で少し触れるが、『城づくり』である。この、彼にしかできない「独自の技術」があったからこそ、彼が「仕官先」を飛び出しても、新しい仕官先は向こうからやってくるようになった。彼は、独自の職能の開発に成功した、比類ない努力の人でもあったのである。

藤堂高虎 銅像
ここに「高山公遺訓200か条」という文書がある。高山公とは高虎の別称である。本人が書き残した200条にも及ぶ、いわば藤堂家の家訓のようなものだが、何せ、200もあるものだから、実にいろんなことが、細かく、丁寧に書かれてある。
例えば、一言半句も嘘を言ってはならない(17条)、高慢な人には先がない(24条)、言葉が多い人は品性がない(25条)といった生き方の基本的な条項のほか、帯の締め方(6,7,8条)や武具の色(10条)にまで言及している。面白いのは第40条で、「10人の主君に仕えた」彼の基本理念がそこに記されている。―――数年、昼夜奉公を尽くしても(そのことに)気の付かない(暗愚な)主君ならば、さっさと暇をとるべし。(そんな上司のもとで)うつらうつらと暮らすのは意味がない―――見事な啖呵だが、それも先述の「独自の職能」があればこその話。
私が特記したいのはこの、200か条の、膨大な家訓の第1条である。―――「寝室を出る時から、今日は死ぬ番であると心に決めよ。」―――彼の遺体は身体中傷だらけで、足も手も指は数本欠損していたという。彼も、あの乱世を命がけで生きていた。権力者の間を要領よく渡り歩きながら、お気楽に、ホイホイと、左団扇で初任給の4000倍の給料を獲得したのではなかったのである。
 著名人から学ぶリーダーシップ著名人の実践経験から経営の栄養と刺激を補給
著名人から学ぶリーダーシップ著名人の実践経験から経営の栄養と刺激を補給