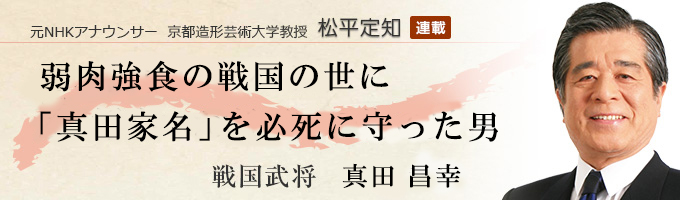真田家は、長野県小県郡真田郷を発祥の地とする。周りを囲むのは、峻険な山々。この山々はその多くが、山伏が修行する霊山である。中でも、真田郷の東に位置する白山信仰の「四阿山」は「山伏たちの聖地」と言われる。その頂上にある「四阿神社」の下社の「山家社」の門前に、真田家の集落があった。いま、そこには、真田家発祥の地を示す、池波正太郎さん揮毫の大きな碑が建っている。そこはコンビニ近くの交差点の角。交差点を往来する車もコンビニ客も結構いて、もちろんいまは何の不自由も感じさせない場所だが、その昔は、行き交う人もあまりいない、ひっそりした寒村だっただろう。
もともと、「真田」は、呪術に長け、その力で「海野、望月、根津」といった家々を束ねていた「滋野」という一族の系統であり、その中の「海野」と呼ばれる家の流れを汲む家だった。初代は幸隆、その息子が今号の主人公・昌幸で、昌幸の息子たちの、信幸(信之)・信繁(幸村)兄弟は3世代目ということになる。

真田昌幸画像
(写真提供:真田宝物館)
この「真田の人たち」は、「峻険な山々」もそうだが、武田、北条、上杉、徳川といった大勢力にも囲まれていた。こうした環境の中で、彼らはどのようにしてその小さな命脈を守り得たのだろうか。それは、彼らに、その「大勢力」の中をうまく泳ぎ切る能力があったからである。その「能力」とは何か。それは「山伏たち」から得る「情報」であった。山伏は修験者だから、通行上の難所はものともしないし、第一、関所の通行が自由である。自由だからいつでも何処からでも、各地の情報を持って迅速に目的地まで辿り着くことが出来る。彼らは、世間で言う「いわゆる『草』」と呼ばれる者に近い「情報の運び屋」でもあった。この山伏たちと真田一族とは、真田の出自の滋野・海野といった「家の関係」から、身近な関係にあったので、真田は彼らから貴重な情報を誰よりも早く、正確に手にすることが出来た。この「情報をもとにした調略」こそが、「大勢力」の中で「小」真田が生き残れた最大の「武器」だったのである。周りの大勢力の一翼、武田信玄は、この「独自のネットワーク」を持つ真田に興味を示し、真田家の始祖と言われる幸隆を家臣とする。幸隆は、信玄がどうしても落とせなかった戸(砥)石城を、その「情報戦略(調略)」によって、武力を使わずに、苦もなく、たった一晩で落としてしまう。ますます信頼を寄せた信玄のもとに、幸隆は長男と次男(信綱と昌輝)を預けた。預けられた二人は、武田勢の中で忠勤に励み、「24将」に数えられるまでの信頼を得る。しかし、その信玄はまもなく病死、後継の勝頼は、真田家の始祖・幸隆が死んだ翌年に起こった長篠・設楽原の戦いで信長・家康連合軍の前に敗退。武田家は「群雄の一つ」の座を失ってしまう。あんなに結束固かった配下の武将たちも、長篠合戦で負けると、他大名の草刈り場になってしまった(その大部分は家康が再雇用するのだが...)。一方、真田家にも変動があった。この「長篠合戦」で、幸隆が信玄に預けていた長男と次男がともに戦死するのである。このため、三男の昌幸が、以後、「真田家」を継いだ。頭をなくして、途方に暮れる武田の諸将を見て、昌幸は沁々と思う。『「親亀こけたら、みなコケた」はイカンな』―――真田家の生き残りをかけて、昌幸は動く。
こうして、初めは武田家傘下だった真田も、長篠合戦の後は織田につく。その信長が本能寺で死ぬと、以後は北条、徳川、上杉、豊臣と、「時の風」を見ながら次から次へと「立ち位置」を変えた。その、あまりの変わり身の速さに、あの、権謀術数の権化の秀吉をして、「表裏比興の者」(「昌幸って、何だか、どっちが表でどっちが裏か、全くわけわからん、恐ろしい男じゃ」)と言わしめたし、家康は家康で、大阪の陣の時、「真田が大阪城に入った」という情報を持ってきた家来に、昌幸は3年前に死んでいるのを承知している筈なのに、手をおいた障子をガタガタ震わせながら「それは父か、子か?」と鸚鵡返しに尋ねたという。要するに、昌幸は、そういう男、だった。
たとえば、二度に亘る上田合戦(「第一次」は、兵の数にして、家康側の5分の1だった真田側が、家康側の大久保彦左衛門をして「徳川軍悉く腰が抜け果て...」と書き記させたほどの大善戦だったし、15年後の「第二次」での昌幸は、秀忠の、「関が原大遅刻」を引き起こさせ、「関ヶ原後」の家康の全国支配青写真に影を落とさせる結果を現出させた。この時の戦力比は、家康対真田、実に15対1であった)などは、昌幸の調略作戦奏功の好例だが、何といっても「昌幸調略の代表例」は、所謂「犬伏の別れ」だろう。
 著名人から学ぶリーダーシップ著名人の実践経験から経営の栄養と刺激を補給
著名人から学ぶリーダーシップ著名人の実践経験から経営の栄養と刺激を補給