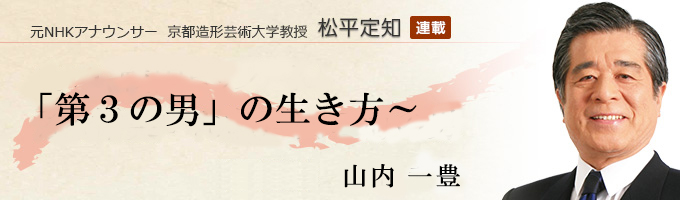越前の朝倉義景軍の勇猛な武将・三段崎勘右衛門は、劣勢の朝倉軍の殿で奮戦していた。そこへ、押せ押せムードの信長軍の一人の武将が勘右衛門をめがけて馬を走らせた。組み討ちを挑んだのである。
剛弓の遣い手として名が高かった勘右衛門はそれを見て咄嗟に弓に矢をつがえ、放った。その矢は、敵の武将の顔面に命中する。矢はその武将の左頬から入り、口中を貫き、右の奥歯にまで届いていた。
天正元年(1573)8月、刀禰坂での出来事である。矢が突き刺さった武将の名は、山内一豊。しかし、一豊はこれに怯まなかった。自分の顔に突き刺さった矢を抜こうともせず馬を走らせ、そのままの状態で勘右衛門に馬上からとびかかった。組み合った二人は坂を転げ落ちた。上になった一豊は勘右衛門の首を切ろうとするが、痛みで腕が動かない。そこへ駆けつけた一豊の盟友(大塩正貞)が勘右衛門の首を斬った。
そのあと、やっと一豊は矢を抜く算段をするが、容易に抜けない。一豊は自分の顔面を泥足で踏んでもいいからと言って抜かせた。抜けるには抜けたのだが、その後の血潮の量が甚しかった。彼は咄嗟に近くの柏の葉を引きちぎって、その夥しい血を拭き、ようやく止血に成功、一命をとりとめたという。
山内家の家紋が「三つ柏」なのは、それゆえだという説もあるが、ま、それはともかく、この時、一命をとりとめたからこそ、彼は晩年に、土佐24万石の大大名にまで出世することになる。この「矢の一件」で、世間は山内一豊を「剛の者」と呼んだ。

山内一豊像
どんなに華々しい戦歴を残しても、後世にその名を残す人物はほんの一握りである。無数といってもいい夥しい数の無名の人たちの死の上に成り立つのが「歴史」、というものであるならば、「剛の者」と後世、人々の記憶に残る人になった一豊は、「持っている人」であろう。
しかも、彼の名が人々の間に残るのはこの一件だけではないとなると、その思いはより強くなる。然し、実はこの「矢の一件」を除けば、どれもがいずれも、賢婦人と言われた彼の妻絡みの話である。それはそれで傾聴に値するが、でも、それゆえにこそ、おそらく唯一ではないかと思われる「彼自身の判断と行動」で掴み取った、この「剛の者」の名声は、是非とも、真っ先に紹介せねばならぬと思った。
確かに彼は戦場では「剛の者」であったが、実生活においては「凡庸な普通人」だった。
彼は天下人ではないし、信長のように自分の実力だけで9分9厘まで天下をつかみ取った大リーダーでもない。天下を狙った男でもないし、黒田官兵衛や片倉小十郎のように、主君の「天下穫り」のために、智謀の限りを駆使して仕えた「超一級のナンバー2」でもない。かといって、彼は天下の趨勢から遠く離れた「その他多勢」でもない。要するに彼の立ち位置は、「第3の男」であった。
律儀で、まじめで、愚直で、本来、あまり目立つことを好まない凡庸な男・一豊は、何よりも妻を愛した。妻も一豊を愛した。一豊は、「出世」については特に野望めいたものは持っておらず、将来的には、山内家を守りつつ、夫婦がこのまま仲良くやっていければそれでいい、くらいにしか思っていなかったのではないか。彼は、妻が才媛で、自分より時代の流れを読むことに長けていることを認めていた。素直な男だった。結婚生活が婦唱夫随であることに何のこだわりもなかった。
「女房の指図で動くのは男の沽券にかかわる」などというような「小さな料簡」は持ち合わせていなかった。しかし、一豊の潜在能力を高く評価していた妻は、天下を目指せとは言わなかったが、彼をより出世させたかった。その「一豊の妻」は、名を「千代」といった。
 著名人から学ぶリーダーシップ著名人の実践経験から経営の栄養と刺激を補給
著名人から学ぶリーダーシップ著名人の実践経験から経営の栄養と刺激を補給