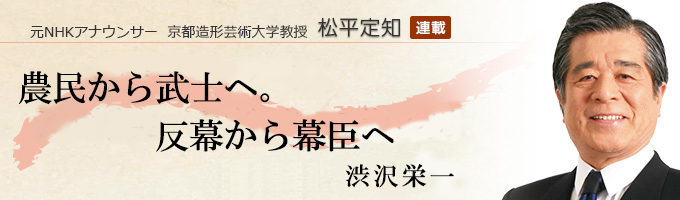円四郎邸から宿に戻ってきた二人はこの夜、よっぴいて議論をします。喜作は言います。「栄一よ。平岡様のご恩は重々感じておるが、でも我々は、これまで、倒幕のために頑張ってきたのではなかったか。今更、一橋家に仕官するのは自分に説明がつかぬ。同志に、あいつら、ついに食うために魂を売ったといわれるのはつらい」。
これに対して栄一はこう言いました。「志のために死ぬことは尊いことかもしれないが、何も果たせずに、志だけで死んでいくのもつまらんとも思う。これから先は自身の行為を以て赤心を漂白するという意思を固めて、どうだろう、試みに一橋家へ奉公と出かけてみようじゃないか。(栄一著『雨夜譚』より)」̶̶̶結局、栄一は喜作を説得し、二人して一橋家に仕官することになります。「武士になりたい」という願いはここで正式に叶います。それにしても、自分のような「武士ではない者」のみならず、「倒幕を声高に叫んでいた者」が仕官できる「いま」を、乱世だと、栄一はつくづく思いました。でも、こうして、仕官しても、その殿様「慶喜」に会ったことは、栄一も喜作もこれまで一度もありません。豚肉好きで写真好き、「新しもの好き」の20代の近代青年にどうしても会いたいと思いました。でも、武士になりたての元農民の身分では慶喜に直接会うことなんかは出来ません。その、段取りをつけてくれたのも円四郎でした。
まず、あらかじめ、栄一らのことを慶喜の耳に入れておきました。そして、慶喜は毎朝馬の調練に出るから、その時を狙い、馬上の慶喜が目の前を通り過ぎる直前に道路脇から出て行って声をかければ. . .というのです。場所は京都の北、下賀茂よりさらに北の松ヶ崎というところ。この「直訴風」の初対面は慶喜の馬のスピードが速かったため一度では成功せず、3度目で叶ったと、司馬遼太郎氏の「最後の将軍」には書かれています。それには、3度目でようやく慶喜警護団が気づき、栄一らを取り囲むと、栄一は刀を鞘ぐるみ抜いて地に捨て、両膝をつき、慶喜の方角を拝した、慶喜は手綱を引きつつ鞭を挙げて栄一と喜作をさし招いたが、その姿は栄一の眼にはまばゆい程に輝いて見え、これこそ、歴史上の千両役者であるように見えた、とあります。その後、夢中で栄一は何かを言上しましたが、聞き終わった慶喜は少しうなずいた後、「円四郎までよく申しておく」とだけ言った、ともあります。
翌日、円四郎宅をたずねると、栄一の身分について、身分は奥口番(屋敷の出入りを管理する役目)、禄は4合二人扶持、ほかに在京手当が月に4両1分、と既に決まっていたとの記述も、前掲書「最後の将軍」にはあります。文久3年(1863)10月末、栄一、一橋家仕官。ここでも才能を発揮した栄一は、翌々慶応元年(1865)には農兵の養成に取り組み、その後、勘定組頭として一橋家の財政再建に奔走する日々を送ります。
翌年14代将軍家茂が亡くなります。栄一は思います。もはや幕府に往年の力はない、今後の日本は、薩・長・土・肥・越前など、全国の雄藩大名が結集した「連合体政治」になるだろうが、その時、彼らを前にことを処していけるのは慶喜しかいない、しかし、幕府という泥船に乗ってしまえば、慶喜も我々も沈んで行ってしまう、だから慶喜の徳川幕府第15代将軍就任に、栄一は反対します。慶喜も、この後継将軍の話を、はじめは辞退しますが、しかし、諸般の事情がそれを許さず、最終的にはそれを受け入れました。これによって、かつての「倒幕・反幕の士」・渋沢栄一は「陸軍奉行支配調役」という「幕臣」に転身します。これは、天下のご直参です。然し栄一の心は晴れません。一緒に仕官した仲良し従兄・喜作と、「こうなってはもう幕府を去って、二人して浪人しよう」と愚痴を言い交わす日々を送っていました。この時、彼らの恩人平岡円四郎はどうしていたのか、とお思いでしょう。実はその平岡は、栄一たちが一橋家に仕官した翌年の、元治元年(1864)6月、水戸藩の尊攘派の林忠五郎、江幡広光に暗殺されていたのです。それまで尊攘派だった栄一が公武合体を言い出したのは、円四郎の入れ知恵によるものに違いないという誤解に基くものでした。平岡円四郎、享年43。
なお、栄一の人生に大きな影響を与えたこの円四郎と渋沢家の因縁は、実は昭和の時代でもあったというお話を是非。栄一のお孫さんに鮫島純子さんという方がいらっしゃいます。今年98歳、今なお矍鑠と、日々を送っていらっしゃいますが、彼女のご主人が航空機の会社で名古屋に勤務しておられたとき、そのお住まいが空襲によって焼けてしまいました。純子さんはじめご家族のみなさんが途方に暮れていた時、「私どもの、茶室が空いていますので、よかったらお引っ越しなさいませんか」と、ご親切にも声をかけてくださった方がいましてね。その方が、料亭の女将になっていた円四郎のお孫さんだった̶̶̶これは鮫島さんから直接、伺った話です。この鮫島さんのお話は次号でもちょっと、触れようと思いますが、まさに「事実は小説よりも奇なり」です。
さて。慶喜公は15代将軍で、沈みゆく幕府の泥船に乗ってしまわれた、私は倒幕の旗も降ろしてしまった、相談すべき円四郎様はすでに亡い、そんな怏怏の日々を送っていた栄一に、慶喜から思いもかけぬ大命令が下ったのは、慶応2年(1866)の11月も末のことでした。その詳細は次号に!
 著名人から学ぶリーダーシップ著名人の実践経験から経営の栄養と刺激を補給
著名人から学ぶリーダーシップ著名人の実践経験から経営の栄養と刺激を補給