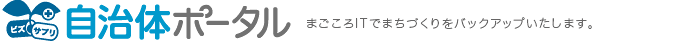
原書房(注2)の成瀬氏とは、昨年の図書館大会の分科会で、運営委員のお手伝いをしたのが縁で知り合いました。近くの図書館で4月19日に「講演会」があると知り、先日の内野氏の講演に通じるものを感じ、参加してきました。
原書房は昭和24年創業の社員20名ほどの会社です。小さな会社に聴こえますが、この業界では中堅どころで、出版社は1,2名の小規模が多いのだそうです。前回の内野氏の「年々出版社が消えていく」話も、出版社の規模を聴いて納得できました。原書房で扱う本はいわゆる売れ筋ではありません、国連の年鑑や地理学の学術書など硬派の書物が多く、半分近くは翻訳書とあって値段も高め。最近は円安で、翻訳の著作権料の支払いも苦しくなったと台所事情も話してくれました。
本はどうして売れなくなったのでしょうか?明らかにインターネットの影響です。本と他の情報との違いについて、時間軸に視点をおいて説明されました。
上記媒体に比べ、本は、著者と出版社が責任を一生負わなければならないとのことでした。
編集の仕事は、企画、著者・訳者・監修者の選定、原稿依頼から原稿受領・整理、レイアウト、校正、資材手配、タイトル、キャッチコピー、装丁、原価計算、プロモーションなど多岐にわたります。一見派手な仕事に見えますが、校正などの地味な作業もあるのです。装丁や字体や紙の質まで、本当に真摯に対応しているのが伝わってきて、出版社は「モノづくりの集団」なんだと実感できました。
最近知人が本を自費出版しました。内容は素晴らしいのですが、レイアウトや字体のせいか読むのに少し抵抗を感じています。今まで本の装丁など気にもかけていませんでしたが、お話しを聴いて、改めて編集者の“こだわり”に納得した次第です。そういえば、このコラムだって同じです。読みやすいレイアウトや校正を担当する編集の方へ、この場を借りてお礼を申し上げます。
日本の本は委託制度に守られています。本ができあがり、私たちが書店で目にするまで以下の流れをとります。
出版社→取次店(卸)→書店(→取次店→書店→出版社(改装))→取次店→書店→出版社→・・・
一定期間書店に置いて売れないときは、出版社に返品されます。その返品率は約4割。凄い比率です。書店に並んでも売れ行きが芳しくないときは、返品された本のカバーを変えて、また書店に並ぶこともあるそうです。出版社は一旦売り上げ計上した本が返品されると負の在庫になります。だから、利益を上げるために新しい本を作るという自転車操業状況に陥ります。都会の大きな書店には山済みになっているベストセラーが、地方の書店では手に入らない矛盾も、取次店がからむ問題だとか。何だかややこしいですね。
図書館に販売するルートには、日販やトーハンなどの取次店を通らずに直接書店や出版社から図書館が購入することもあります。著者や出版社は本を売らないと利益にならないので、同じ本を何度も貸出する図書館は「無料貸本屋」との批判もあります。著作権料の視点から見ると、実はもう一つ抜け穴があり、それはBOOKOFFなどの古書店マーケットです。古書店で買い求められた本も図書館と同じように著者には著作権料は入りません。これが問題視されないのは、経済の法則に従っているからなのでしょうか。
図書館と書店の違いを、「書店は“経済”、図書館は“政治”」と、某書店の店長が喩えました。年間8万冊もの新書が出る中、書店とて全ての本を並べることはできません。だから、売れる新刊本が中心になり、書店は売るための“棚”をつくります。書店で売れない本には色々あります。高価すぎて買いたいけど手が出ないのも書店では売れない本に属します。売れない本は売れないだけで、役に立たない本でも使えない本でもないのです。図書館には、これらの売れない本も“棚”に並びます。
ほとんどの出版社が、それでも本を作っていくのは、数少ない売れた本の利益で食いつないでいるとのことでした。そして、その利益に図書館が大きく貢献しているというのです。硬派の出版物の初版発行部数は2000部が平均。公共図書館は約3000。もし公共図書館の3分の1が買ってくれれば、充分採算が取れるというわけです。
補足ですが、昨年の図書館大会で成瀬氏が話していたことも紹介しておきます。
「本当はその先の本を手に取ってくれる読者をみなければならないのに、編集者は著者に目が向いているし、営業は取次店に目が向いています。出版社は直接読者と関われないもどかしさがありますが、図書館は直接利用者と関われる利点があります。出版社からみれば図書館もまた読者です。図書館に本を置いてもらえることは信頼感にもつながっていきます。図書館には多くの方が来館し本を手に取るので、図書館に置いてもらえる本を作れば出版社の質も上がります。」
ある利用者の方が、成瀬氏に「度々図書館へ借りに行き、あまりに独り占めしているのは気が引けて、遂に購入しました」と連絡をくれたそうです。これこそ成瀬氏の想い描いた販売ルートです。図書館は“ショールーム”の役割を果たしたのです。どんな著者やどんな作家も実は図書館のヘビーユーザーでした。図書館には役に立つ使える本が棚にあるからです。「図書館と書店が共存できる道を探す」成瀬氏のテーマは、出版社が「図書館を通じて読者とつながる」ことでもあるのかなと感じた講演でした。
最後の質問タイムでは、再販制度やWeb直販の問題点など厳しい質問も飛び出し、正直に答える成瀬氏の人柄にも好感が持てました。お忍びで参加されていた某指定管理者の方から、「西葛西はセミナー参加者の意識が高い」と言われ、何故だか地元愛を感じた私でした。
何やら怪しげなタイトルですね。
図書館システム(コンピュータシステム)の歴史は古く1970年代には既にシステム化されていました。コンピュータ化されるときに、各社独自の仕様で走ってしまったつけが今も残っているのが現実です。例えば、貸出されている本に予約がかかった時の流れ一つを取って見ても、システムにより扱いも言葉も違います。以前、有志で、システムごとの違いを比較しようと試みたこともあったのですが、諦めました。片手間でできるほど安易なものではなかったのです。
私たちが手掛けていたシステムも独自の言葉がありました。例えば、予約本を確保した時の状態を「別置(べつおき)」と呼んでいました。他のシステムから移行したユーザーが増えていくにつれ、この言葉が、混乱を呼びました。別置記号の別置(べっち)と紛らわしいというのです。パラメータを設定して、ユーザーごとに言葉を変える選択もありましたが、プログラムが煩雑になります。そこで「別置」の言葉を変更しても構わないかと、ユーザーの皆さんにアンケートをとらせていただきました。
その時に、唯一こだわったのが、M市図書館でした。図書館に直接出向き、言葉の変更をお願いしたところ、N館長から、「図書館では“別置”というハンコも押しているからダメ!」と返事が返ってきたのです。そこで私、「ハンコは私がポケットマネーで購入させていただきます。言葉の変更にご協力ください」とすがりました。これにはN館長も根負けしてくださいました。かくして、予約本確保の言葉は、皆さんの了解を得て、「棚置」に無事変更することができました。私たちのシステムは直接ユーザーとの接点があったから、こんなやりとりも可能だったのです。
N館長とは、図書館の右も左も解らない頃からのお付き合いで、図書館の「イロハ」を教えていただきました。ちょっと茶目っ気のある、忘れられないエピソードです。