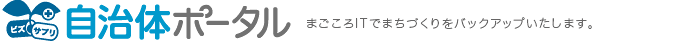
紙とデジタルの読書については、「デジタル社会は子どもの読書環境をどう豊かにできるか?」シンポジウム(注1:第110回コラム)で紹介したことがあります。子どもたちに1人1台パソコンが支給される時代。電子書籍はもとより、レファレンスがGoogle検索で事足りれば、辞書や辞典などのレファレンスツールは必要なくなるのか。
図書館見学が続いたので、今回は、辞書・辞典から文献目録までレファレンスツールを多く出版する日外アソシエーツ株式会社の内部勉強会に参加させていただいた報告です。
講師は、知人の結城俊也氏。専門理学療法士として患者に向き合う一方で、医療福祉学博士の立場から、各地で健康医療講座を開設しています。講演は、身体的認知論の視点から、このテーマに迫りました。ちなみに、「身体的認知論」とは、思考や判断などの認知は身体の働き(感覚や動作)を基盤にしているという理論。小さいころそろばんを習っていた友だちは、今も計算するときに頭の中でそろばんをはじきます。物事を考えるときは、腕を大きく回す動作により思考が広がり創造的なアイデアが生まれやすいなど。子どもが言葉を学ぶときも、特定の姿勢や動作と関連付けることが手助けになるとのこと。動作がないと言葉は学べないのだそうです。
出版社が生き残るための2つの視点からの話でした。
私たちが横書きの本を指でなぞったり、書き込んだりしながら読むときは、本を利き手とは反対方向に(右利きの人は左に)5度ほど傾けた方がやりやすい。なぜなら、なぞったり横書きしたりする際、肘関節を中心に肘から先の手を回転運動させると腕全体の動きが小さくなり、腕も安定するからだそうです。いわれてみると、確かに無意識ですが、そうしています。タブレットにも本と同じように紙をめくるような機能があるのに、なぜだかしっくりこないのは、タップの位置やスワイプの力具合など認知負荷が高くなるからで、集中度では紙の方に軍配が上がるそうな。とはいえ、デジタルネイティブの子どもたちは生まれたときから慣れ親しんでいるから、私世代のような負荷感覚は少ないかもしれません。
一番印象に残ったのは、「文章は目ではなく、手で読むもの」ということです。紙は単なる表示メディアではなく、五感(大きさや形や装丁・紙の香り・めくる音・感触・重さ)を使い、手を使って書籍のメッセージをつかみ取る操作メディアといいます。これらの慣れ親しんだ操作性が「紙」の優位性だというのですが、「デジタルでもできるのでは?」との質問がありました。これに対し、身体との相互作用の話になり、紙の本は外部リソースとして、思考や行動がつくられる周囲の環境へと展開していきました。私たちの集中力はせいぜい15分。天井が高い場所にいると人は思考が広がり、曲線は人間に安心感と心地よい感覚を抱かせるなど、建物との関係性なども実に興味深く拝聴しました。紙は薄くて、軽くて、柔軟性があるからこそ、いろいろな姿勢で持ったり、めくったり、運んだりと、アフォーダンス面を指摘。アフォーダンスとは認知心理学の概念で、例えば公園にベンチがあれば私たちは「座るもの」と認識します。行動を促したり制限したり「ほのめかす」環境文化をいいます。「知の巨人」といわれる松岡正剛氏によれば、読書は複合的行為であり、本の姿勢や雰囲気、図書館や書店という空間も「読書」に含まれるそうな。家では集中できないけど、図書館では集中して勉強できるのは、そんな裏付けがあるのですね。
AIにはリンゴをかじったときの酸っぱさなどの身体を通しての経験はできません。さまざまな感覚情報は、それがまつわる感情がつながって、経験値として記憶されます。記憶は五感とセットで記憶されるから、「りんご」一つとっても、思い浮かべる情報は人それぞれ違います。回想法(注2:第33回コラム)がツール(道具)を導入に使うのは理にかなっているのだと、思わぬところとつながって一人で納得していました。
ということで、紙の本が人間の身体と親和性の高い操作メディアである以上、今後も認知を行う上で重要な外部リソースとなるのではとのことでした。
図書館では、本の貸出だけでなく、レファレンス・サービスも行っています。レファレンスとは、何らかの情報あるいは資料を求めている利用者に対して、司書が相談に乗ることで、求められている情報あるいは資料を提供ないし提示するサービスをいいます。例えば、「納豆について知りたい」という利用者の問い合わせに、司書は納豆の何について知りたいのか。具体的に聴いていきます。料理? 発酵食品のこと? 大豆栽培農業? などなど。利用者と司書とのコミュニケーションが解決へのヒントにつながります。コミュニケーションには、非言語コミュニケーションも含まれます。声のトーンや仕草やジェスチャー。利用者が首をかしげて反応したら、それは違うということです。相手が何を感じているかを自分の身体で感じ、相手が満足していないようなら、司書は新たな模索を続けるコミュニケーションのキャッチボール。身体論から考えるレファレンスに必要なことは、非言語も含めたコミュニケーションと五感を通した共感。とりわけ、身体を持たないAIには、非言語的コミュニケーションが苦手という話に、マスク生活を余儀なくされたコロナ禍に生まれ子どもたちの発達に、改めて危機感を覚えました。今のところAIには、時間と距離が表現できないこと。それは相互に関係性を持てないからだそうで、確かにZoomとリアルに会ったときの満足度の違いに似ています。
結論として、質の高いレファレンスを行うためには身体的な相互作用を通したコミュニケーションが必要で、現時点では身体を持つ人間の方が優位ではとのことでした。
身体の状態や動作が人の認知にどうかかわるかという身体的認知論なるものも初めて耳にしました。
そうはいっても、デジタル書籍が優位な点もたくさんあります。例えば、書き込みは消せるし、本のように重くはなし、大量のデータが取り扱えます。本と電子を区別するのではなく、用途に応じてメディアの使い分けを行うと、今回も着地点はお互いをリスペクトすることで落ち着きました。
興味を持った方は、結城氏お薦めの本、メアリアン・ウルフ著『デジタルで読む脳 X 紙の本で読む脳 :「深い読み」ができるバイリテラシー脳を育てる』も是非!